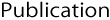CSP1シンポジウム 2013.11.30
「自分のつくったものが他の文脈に食べられる事について」
登壇者
大畑周平、狩野哲郎、末永史尚、タノタイガ、Mrs.Yuki(平嶺林太郎、大久保具視)
モデレーター
栗田大輔

●第一部
- 母袋:
-
東京造形大学の母袋と申します。よろしくお願いします。まもなく定刻となりますので、シンポジウムを始めたいと思います。その前に、CSP1という展覧会について、簡単な概略と経緯などをお話させていただきたいと思います。
昨日から「CSP1 - Amplitude 場への働きかけ -」という展覧会が始まっておりまして、本日はシンポジウムとレセプションが行われる予定です。今回の展示はとても刺激的なものになったのではないか、企画者の一人として自負しております。
出品者のみなさま、本当にありがとうございました。
本プログラムは、造形大の絵画の生嶋順理先生、彫刻の保井智貴先生と母袋が卒業生の活動を照射し、学外への発信、記録化をしていきたいという共同の思いから出発しました。学内的には絵画と彫刻、この二つの専攻から構成される美術学科初の共同プログラムでもあります。
二つの専攻はそれぞれの原理に沿って教育プログラムを進めていくのが前提ですが、大学の外側ではこの専門性に分けて捉えていくというような考え方、あるいはアスペクトそのものが有効性を失って久しいようにも思っています。
良くも悪しくも、アートシーンはダイナミックに変貌を遂げています。しかし、このようなシーンとは異なる美術へのアプローチが、教育・研究機関である大学としての大きな使命であるのだという考えがあったのです。
CSPは今回を含め3回連続開催し、その活動は展示のみならず、シンポジウムなどを含めたコロキウムとして、議論と問題提起をしていく場として、3年を目処にその記録化を目指します。
CSP第1回目の今回は、「CSP1 - Amplitude 場への働きかけ -」という副題がついています。今回出品している7名の作家をはじめ、造形大学出身の作家には、自ら積極的に発表の場に働きかけをするという特徴があったように考えられ、そこからの命名であります。もちろん、この「場」とは、単に「site」の意味を指すわけではなく、広義の意味を持っています。それは、あるいは「領域」ということであるのかもしれません。
粟田大輔さんをモデレーターに、出品作家の方々で行われるこのシンポジウムは、「自分のつくったものが他の文脈にたべられる事について」、とのタイトルがついていますが、その文脈そのものの場であるかもしれません。
以上が今回のCSPについての概略と経緯になります。それでは粟田さん、進行の方、よろしくお願いします。
- 粟田:
-
 ありがとうございます。モデレーターを務めさせていただきます粟田と申します。登壇者の方をまずご紹介しましょう。私の隣から末永史尚さん、狩野哲郎さん、大畑周平さん、タノタイガさん、そしてこちらの二人が、Mrs.Yukiというユニットを組まれている平嶺林太郎さんと大久保具視さんです。
ありがとうございます。モデレーターを務めさせていただきます粟田と申します。登壇者の方をまずご紹介しましょう。私の隣から末永史尚さん、狩野哲郎さん、大畑周平さん、タノタイガさん、そしてこちらの二人が、Mrs.Yukiというユニットを組まれている平嶺林太郎さんと大久保具視さんです。
辻直之さんは、本日はご都合が悪くて、残念ながらシンポジウムには出席されません。こちらの会場では、一番奥のアニメーション作品を展示されていたのが辻さんです。
今回のシンポジウムのタイトルは、事前の打ち合わせで、今、母袋先生から紹介があったような問題意識の中から、どういうシンポジウムをやればよいのかを話し合っていたときに、辻さんが、「自分が作った作品が、他の文脈に食べられることをみなさんどう思っているんでしょうかね」とぽろっと言ったことがきっかけになっています。
今回、辻さんが出席できないということもあり、こういうことを少し自分たちが引き受けてしゃべってみましょうかということで、タイトルにさせていただきました。
今回のシンポジウムは5時までを予定しており、ゆるやかな二部構成を考えています。第一部では、今ご紹介させていただいた作家の方に、自分の作品についてのプレゼンを各5分程度していただいて、そのあと、簡単に1、2分質疑の時間を設けさせていただくかもしれません。そして、途中で軽い休憩をはさみ、後半にシンポジウムのタイトルに掲げた問題について、登壇者で話をしていきたいと思います。
では、早速、大畑さんから作品のプレゼンをしていただきたいと思います。よろしくおねがいします。
- 大畑:
-
こんにちは。大畑です。既に見られた方もいるかもしれませんが、白い長テーブルを展示しているのが僕の作品です。
これは、パフォーマンスというか、イベントをする際に使うものです。今迄何度も発表している作品ですが、展覧会という形では初めてになります。本来は一瞬で完結するものを会期中延々と見せる事に少し戸惑いがありました。テーブルも自分では彫刻の台座の役割と結びつけて考えているように、美術の問題としても捉えていますが、それはイベントを行う時だけ、人とモノとの関係によって生じるものだからです。
でも、展覧会とイベントでは同じテーブルでも見え方が変わってしまうのは面白いと思いました。それで、展示では作品としてではなく、会場の雰囲気を作り出すインテリアとして扱っています。長さが8メートル程あるので、会場の動線にも少なからず影響を与え、展示空間を構成する要素として組み込まれていると思います。
テーブルの上に目を向けると燭台や、石のプレートが並び、端に二台のトイピアノが向かい合って並んでいます。こうした小道具を使ってどんな事を行うか少しお話ししたいと思います。これは参加者とともに火を食べるというイベントなんです。先ず、参加者に火を食べませんか?と募集を募り、火を食べるってどんなものか興味を持った方が集まって一緒に火を食べます。本当にそれだけ。でもそれだけの為に空間を作り込んでいます。
会場の照明はテーブルの上の燭台の灯りだけ。二人の音楽家によるトイピアノやアコーディオンによる演奏が始まると石のプレートには火を食べる為のオリジナルチョコレートが並べられていきます。このチョコレートは蝋燭のように燃えるように出来ていて、火を付けた状態のものを食べてもらいます。芯にあたる部分も燃料となる油分もすべて口にいれても問題ないように出来ています。準備が整った段階で、音楽も終わります。それから、僕が食べ方の説明をして一斉に点火します。2、3分テーブルにひろがった火の景色を楽しんだところで、参加者それぞれのタイミングで食べていきます。中々口に出来ない人もいれば、簡単に食べてしまう人もいる。食べられない人にとっては迷惑かもしれないけど、たまたま会場に居合わせた人に応援されたりと様々なドラマが勝手に展開している。
参加者ははじめ、火の着いたチョコレートを眺めているだけです。それが火を食べる時には、自分で手にとって口に運ばなければなりません。やってみると結構怖いので、他の人はどんな食べ方をするのか、自分だけでなく会場にいる参加者の姿が気になります。この段階で食べる人へと関心が移るんですよね。つまり、参加者は見るだけでなく見られるという状況に置かれます。
また、僕はイベントを企画しますが、火を食べてくれる参加者がいなければ、作品として完成しない。自分でも作るけど、作ってもらっているんです。こうした発進する側と受け取る側の関係が行ったり来たりする事で、火についてはもちろん、人と人との関係や人とモノとの関係について僕は考えるし、参加者にも後で、あの体験って何だったのか?ふと思い出して貰えればと思っています。
 火を使った作品を作り始めたのは、2000年頃からです。これは、ポンポン船と呼ばれるおもちゃをモチーフにしたもので、船体が蝋で出来ているのが特徴です。火を着けると進みますが、そのうち溶け出して船は沈んでしまいます。PHILIP MORRIS K.K ART AWARDという2002年に開かれたコンペに出品で一次審査が通って最終審査を兼ねた展覧会に参加したのですが、会場では火は使えないという状況になり映像を使って見せることにしました。火を付けて、お客さんに楽しんでもらうというところまでが作品だったのですが、公共空間で実現することの難しさを感じました。
火を使った作品を作り始めたのは、2000年頃からです。これは、ポンポン船と呼ばれるおもちゃをモチーフにしたもので、船体が蝋で出来ているのが特徴です。火を着けると進みますが、そのうち溶け出して船は沈んでしまいます。PHILIP MORRIS K.K ART AWARDという2002年に開かれたコンペに出品で一次審査が通って最終審査を兼ねた展覧会に参加したのですが、会場では火は使えないという状況になり映像を使って見せることにしました。火を付けて、お客さんに楽しんでもらうというところまでが作品だったのですが、公共空間で実現することの難しさを感じました。
それで、普段使われていない場所や店舗などでも発表するようになっていきました。これは、昔の茨城県県庁舎だったところなんですけれど、4階建ての一番上の部分が増築していて、県庁舎として使われなくなったあと、三階までは公民館として使われていました。法規的に4階の部分は施設として使えない場所だったけど、中々雰囲気のある空間だったので映画のロケーションなどで貸し出すことはしていたんです。たまたま縁があって借りることが出来たのですが、残念ながら311以降4階部分は解体されてしまいました。
最後に、 来週このイベントを予定しているのですが、一つお断りしなければいけません。出演予定だった音楽家の阿部海太郎さんの体調が優れなくて、別の音楽家が担当します。また、来週5時から予定していたのですが、6時からの変更になってしまい、ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。まだまだ受け付けていますので、ぜひ体験してみてください。ありがとうございます。
- 粟田:
-
ありがとうございます。今の作品は、60年代ぐらいに、草月ホールなどでオノ・ヨーコとかがパフォーマンスなどをやっていたところとも、少し関係してくるのかなと。そうした歴史的な文脈も踏まえているのかなとちょっと思いました。
今日のプレゼンでおもしろいなと思ったのは、火をどういうふうに考えるのかということでした。確かに僕らはコンロをひねれば火が見られるわけで、火の現代性、火を、大畑さんはどういう風に見ているのですか?
- 大畑:
-
ガスコンロも今や電磁調理器へと変わっているように、現代では、火が生活から遠ざかっていると思います。 もちろん合理的ですし、その流れを否定するつもりはありません。
でも、火の持つ怖さ、美しさ、不思議さに触れる機会を失うと、僕自身の感覚で言うと、感受性が鈍くなる気がします。だから制作を通して火と関わりを持とうとしているのかなって思います。最近は、食をテーマにした作品を作っていますが、この火を食べる作品では、人は結局何を食べているのかなという疑問から生まれたんです。それで、エネルギーを食べていると思った。料理は火というか熱の加減が重要ですし、果物など生で食べられるものは、太陽の熱によって料理されている。色んな食べ物が世の中にはありますが、その中で、共通する本質的な要素として、エネルギーだけは関わっているからです。
それから、火が興味深いのは、火という現象は確かにあるのだけど、僕たちは火そのものを食べる事が出来ないということです。料理は火や熱が加えられていますが、食べられるのは火の痕跡だけなんですよね。
- 粟田:
-
ありがとうございました。では、次に狩野さんお願いいたします。
- 狩野:
-
こんにちは。狩野と申します。今回は、会場の入り口を入って、正面にある長い壁の手前に、彫刻的な作品を7点ほど出しています。僕は最近、自然物を使ったインスタレーションをよくやっています。
これは、学生の頃の初期の作品で、室内の美術館的な空間の中に、カーペットが敷いてありまして、その上に雑草の種をまいて草を育てる、そして展覧会の会期中に、育ったり枯れたりするという作品です。
これは、本物の鳥が出てくる作品なのですが、美術館の空間の中に電気のコードがあったり、プランターとか、漁業の網だったり、スーパーボールなどのおもちゃだったり、海の砂とかが配置してあって、その中に本物の鳥が放し飼いにされています。モルディブという国で展示をしたのですが、現地にいるマイナという鳥が、会期中ここで生活をしていました。柵の中に、例えば今回の作品の中にもあるのですが、果物や植物の種などが置いてあります。それが色や形としての造形作品の要素でもあり、動物の餌にもなっています。
 これは、今回の作品に近いシリーズなのですが、「野生のストラクチャ」というタイトルが付けられていて、陶磁器やガラス、プラスチックの容器、ペット用のおもちゃなど、いわゆる製品を組み合わせて、塔や都市のような形の彫刻を作っています。やはりこれも、いろいろなものを組み合わせて造形物を作ると同時に、本物の鳥を放し飼いにして、動物のための新しい自然というか、手作りの環境としての造形がされています。
これは、今回の作品に近いシリーズなのですが、「野生のストラクチャ」というタイトルが付けられていて、陶磁器やガラス、プラスチックの容器、ペット用のおもちゃなど、いわゆる製品を組み合わせて、塔や都市のような形の彫刻を作っています。やはりこれも、いろいろなものを組み合わせて造形物を作ると同時に、本物の鳥を放し飼いにして、動物のための新しい自然というか、手作りの環境としての造形がされています。
これは下にも展示している作品と同じシリーズの別のものなんですけど、白い部分は、取り替えができるキャンドルスタンドになっていて、集めてきた木の枝を生け花のような感じで組み合わせて、それを鳥がついばみにきて使います。このときは個展だったので、会場の中に今回置いているような彫刻作品が点在していて、その中に鳥がいて、彼らが自分たちにとって有用なものを選んだり選ばなかったりするというものが会場の中では見ることができました。
今回は、鳥もいないですし、台座の上にのっかっていたりとか、照明などの演出もいわゆる彫刻作品を作るときのセオリーに非常に近い形で展示をしています。
作品を作るときには、人間以外の植物や鳥にとっての価値という一つの軸と、もう一つ美術の作品としての色彩だったり、形態であったり、質感をどう組み合わせて造形物として成立させるかということを同時に扱っています。
- 粟田:
-
ありがとうございます。Mrs.Yukiの問題とも関係してくるかもしれませんが…。動物の問題というのは、近代では、人間とは何か、人間の感性とはどういうものなのかというのが哲学的に議論されてきたのですが、近年は、むしろ動物の哲学だとか、動物という問題をどういうふうに考えるかというところが注目されているので、そういった点からも興味深いなと思いました。生物から見た世界とかですかね。
一方で、彫刻の問題もおっしゃっていましたが、末永さんはどうですか? 今回の展覧会は、みなさん出品作家なんですが、展示の実行委員としては、末永さんと大畑さんが関わられていて、実は壁を設計されたのが末永さんです。その点から、今回の狩野さんの作品についてどう思われましたか?
- 末永:
-
末永です。狩野さんの作品は、学生のときから知っていたのですが、しばらく見ていなくて、久しぶりに見たら、展示される環境に対する狩野さんの反応の仕方が非常におもしろいと感じました。
今回もああいう白壁ではない、非常にクセの強い壁に対して、狩野さんがどういう風に反応するのかということを非常に楽しみにしていました。狩野さんが持ってきていた作品を収めるためのパッケージに使っている、壁材と同じもので作られたクレートをうまく作って、処理というか違和感なく作品をおさめていたので、すごくおもしろかったです。
- 狩野:
-
実は、造形大学の学部のときは、立体系のデザインのコースに所属していまして、大学院に進むときに絵画のコースにお世話になったのですが、大学院に入ったときに、最初から先ほどお見せしたような、空間の中に植物を配置する作品をすでにやっていました。
もともと絵画や彫刻をやっていてインスタレーションに移行したというのではなくて、空間を考えるということからそのまま、インスタレーションに入ったんです。自分で作るときに考えるんですけど、平面の作品も立体の作品も作っているけれど、いわゆる画家・彫刻家は、展覧会の会場のどこにどういう比率で、何点の作品をおさめるかということを当然考えると思うんですけど、自分の場合は例えば、展示会場で与えられた壁にどこまで手を入れるべきか、もしくは触れないべきか、ということも同時に考えるクセがついています。
最近のシリーズは、自分の中では彫刻的だと思っているんだけれども、自分が用意した彫刻の運搬用の木箱を展示台として使うか使わないかという判断があって、あんまり彫刻自体の展示のセオリーと関係がないところもある。そのズレみたいなのが、自分の特質というほどではないけれど、個性の一つなのかなと前向きに、何か反応すべきところがあったらやってみようかなと思っています。今回も割とクセの強い壁があったときにどうするかというのは自然に…。
- 粟田:
-
ありがとうございます。では、続きましては末永さんよろしくお願いします。
- 末永:
-
末永です。入って左側の壁に、6点展示しています。僕の作品は、展開がいくつかにわかれていて、与えられた5分の中では全部紹介しきれないので、今展示している作品のシリーズ、「タングラム・ペインティング」シリーズと名付けているんですけれど、これに絞ってお話したいと思います。
この作品は、今展示しているものと同じなんですが、組み方によって形を変えることができます。この作品は、下で入り口側に近いところにある作品と同じ作品、これも上の方に展示しているのと同じものなんですが、組み方によってはこのように異なる形にもなります。でも、全ての作品が正方形に組み直すことができて、絵自体は、この正方形の状態で描いています。正方形は、60cm×50cmで、組み直すとだいたいこのような形になります。
 タングラムというのは、もともとは中国で作られたシルエットパズルで、シルエットで出題されて、その形に組み替えることができるかというのを楽しむパズルですね。僕の場合は、展示状況に合わせて形を変えられるという仕組みをつくっています。この作品自体を作ったのは2008年くらいなので、もう6年くらい前になります。そこから断続的に作り続けています。
タングラムというのは、もともとは中国で作られたシルエットパズルで、シルエットで出題されて、その形に組み替えることができるかというのを楽しむパズルですね。僕の場合は、展示状況に合わせて形を変えられるという仕組みをつくっています。この作品自体を作ったのは2008年くらいなので、もう6年くらい前になります。そこから断続的に作り続けています。
このスライドは、「タングラム・ペインティング」シリーズを作り始めたきっかけの展覧会の写真なのですが、2008年のニューバランス展という、茅場町にあった「gallery Archpelago」というところで開催したものです。冨井大裕さん、村林基さんと3人でやった展覧会です。このときに、会場設営をお願いした田中裕之さんという建築家の方に、展示の前にお題をもらいました。そのお題が、展示空間の上下の半分の高さに透明な水平な線があると仮定して制作しなさいというものでした。「どうしたものかな?」と考えているうちに、「どのような壁面の高さであっても展示できる作品を作り、それを田中さんに展示してもらえばいいんじゃないか」ということを考えて制作したのがきっかけです。会場では田中さんが組み直して展示をしています。
僕自身は、組み直して平面的にいろいろな形にすると考えていたんですけれど、田中さんは建築家なので、立体的に彫刻的な感じで使ってしまったという。その直後の個展ではこういう風に自分で平面的に組み替えて展示しました。
ニューバランス展のために作った作品ではあったのですが、もともと僕が持っていた問題意識、つまり、日本という環境の中で絵画を作るという事に対して、大きい絵を作っても、行き場がなかったり、制作する環境がなかったりということを逆手にとって何かを作れないかという意識があったので、いろいろな状態の中で展示できる作品というのは、まさにその回答のような気がしていて、その後も作り続けています。
これが、それをちょっと大きく展示する機会があったので、参考に持ってきたのですが、秋吉台国際芸術村という僕の故郷の山口にあるレジデンス施設兼音楽ホールで展示したときの写真です。これは音楽ホールを使った展示です。会場自体は磯崎新さんの設計で、変わった形をしているんですが、もともとは、これができたときの記念公演、《プロメテオ》という現代オペラのために設計されています。普通の音楽ホールだと、ステージがあり、客席がありというふうに、「見る」、「見られる」という関係があるのですが、ここではその関係を作っていません。客席がステージにもなりうるし、ステージになるはずの中心部分もフラットにして、客席にすることもできるという構造になっています。
その構造で作られたのですが、そこから10年以上経って、普通の音楽ホールとして使われることが多くなっていました。そこで、こういう展覧会の機会を使って、もう一度会場のおもしろさを生かしてほしいという依頼で展示をしました。
磯崎新さんの会場の形態的なモチーフは、この近くにある秋芳洞という鍾乳洞がモチーフになっています。その形のイメージを取り戻すことができないかなということで、入り口から会場にあった台をパーテーションがわりに使って迷路のようにしてということをしました。
- 粟田:
-
金沢21世紀美術館が建設された時期に、学芸員とかが設計に介入して、どういう展示空間をつくろうかという議論がされて、だんだんそういうことがされるようになってきたのかなと思います。「アーツ前橋」という、前橋にできた新しい空間もそうですね。
ただ、60年代とか70年代の美術館とか、こういうホールが作られたときというのは、割と建築家の独断で作られて、「なんでこんな空間できちゃったんだろう? 使いにくい空間だな」とかいうのをよく耳にすることがあって、実際にそういう空間は、日本の文化ホールとかに多いと思うんですけど…。
末永さんが先ほどおっしゃっていた「環境を逆手にとって」というのがおもしろいなと思いましたけど、秋吉台国際芸術村の場合は、もう一回建物の構成なんかも末永さんの作品を通して読み取っていけるし。
今回の下の場所は、そういった意味では非常に「環境を逆手にとって」ということに、すごくフィーチャーされている作品だと思いました。ありがとうございます。
では、続いてはタノタイガさん、お願いいたします。
- タノ:
-
ちょっと僕だけ、発表の趣が違うかもしれないのですが…。タノタイガといいます。東京都中野区生まれ、宮城県仙台育ちでございます。生まれたときの体重が3470グラムで母子ともに健康で生まれました。好きな食べ物がえび。ぷりぷりとした食感が好きなんですけれども。趣味は、料理、旅行、ダイビング。マイルをためること。そして節税です。
これは、今年の夏にスペインを母親と旅行したときの写真です。ちょっと話しが逸れましたが、資格は普通自転車免許、中型運転免許を持っています。あと、中型自動二輪免許。一級船舶免許。それからレスキューダイバーの資格も持っています。
今年、スペイン語の国際検定でB1というレベルに合格しました。性格は好奇心旺盛。人生の半分は遊んでいないと死んでしまうという性格の持ち主です。
では作品の話に入りたいと思います。
今回出品している「15min.ポートレート」なんですけれど、この作品は、2008年から継続的に作っているもので、今年も撮影には行っているんですけれども、それを出品しています。
ここでお見せしているのは、下に展示している写真とは違う、最近の写真です。これは15分間で撮ったポートレートです。日本のとある南の島で撮影をしているんですけれども、その土地には基地の問題があったり、所得水準や教育水準が一番低いといった特異な環境、日本でありながらも東京なんかと比較すると、ちょっと特異な環境の島です。そこにはまだ置屋と言われる売春宿がいくつか残っています。そこで、お客として僕が入って、決められた15分という単位のお金を払って、その娼婦の着ている洋服を借りて僕が着て、娼婦に僕の写真を撮ってもらうというプロジェクトを2008年から継続的にやっています。
継続的にというのは、ものを作るというのは、一瞬になってしまうことが多いんですけど、僕は、作品を作るということの捉え方が少し変わっているのかもしれません。こういう街がどんどんなくなっていっているんですが、その街がなくなるまでか、僕の中で一段落するまで、ライフワークとして続けようと思っています。メディアとしては写真なのですが、正直僕としては、写真にすることすら、こうしてお見せすることすらあまり必要ではないのかなとさえ、最近は思っています。
なぜこういうものを作るのかというと、私たちの社会は効率とかシステムとかいうものに縛られて生きているわけですけれども、ある意味、売春宿みたいな今の日本の国ではもちろん違法なことではあるんですが、それはわずか数十年前には国が管理して、善であったものです。善の側にあったものが、ある瞬間から悪に変わるという。先ほど旅行が好きと言いましたが、いろいろな国を回っていて国境を越えた瞬間に善悪の判断が変わっていくということを、同じ時代、同じ人間でありながらも、そのいびつさを感じることが多くて、これを続けています。
こういったことにはいろいろな問題がつきまとうわけですけれども、僕は行ったこともない、見たこともないことに対して意見をするのはあまり好きではありません。なので、自分は体験主義というか、ここで15分の間でも僕は数を重ねることで、彼女たちの置かれた環境とか生活とかを知ることができることができるから、彼女たちの良いことも悪いことも、ダメなところも許容することができるのではないか。それに対して発言することができるのではないかという思いで、僕は身を置いているという行為です。
今回の作品はそういう感じで2008年からのもので、今手元にあるものの3分の1くらいの写真の数ですが、下に展示しています。
 「モノグラムライン」シリーズというのは、2004、5年くらいからしばらく作っていたシリーズで、木彫でルイヴィトンのバックを作り、色鉛筆で彩色するという作品で、これはギャラリーでももちろん展示するんですけれども、その時に上に「LVM¥〜〜」とか書いているのが見えると思うのですが、これは作品のタイトルです。価格も作品に含まれているのですが、僕が作るルイヴィトンの彫刻を、この値段で売買するという目的で作られています。これはルイヴィトン側によって僕の作品の価値を決められているという前提で彫刻を作っている作品です。この作品を作るともちろん、商標権の問題とか法律的な問題が出てくるんですけれども、それを実験してみたいなということで、ボーダーラインプロジェクト、ルイヴィトンの木彫を肩から提げて飛行機に乗って、パリのルイヴィトンまで行き、日本に帰ってきて国境を越えられるかというプロジェクトをやったりしています。
「モノグラムライン」シリーズというのは、2004、5年くらいからしばらく作っていたシリーズで、木彫でルイヴィトンのバックを作り、色鉛筆で彩色するという作品で、これはギャラリーでももちろん展示するんですけれども、その時に上に「LVM¥〜〜」とか書いているのが見えると思うのですが、これは作品のタイトルです。価格も作品に含まれているのですが、僕が作るルイヴィトンの彫刻を、この値段で売買するという目的で作られています。これはルイヴィトン側によって僕の作品の価値を決められているという前提で彫刻を作っている作品です。この作品を作るともちろん、商標権の問題とか法律的な問題が出てくるんですけれども、それを実験してみたいなということで、ボーダーラインプロジェクト、ルイヴィトンの木彫を肩から提げて飛行機に乗って、パリのルイヴィトンまで行き、日本に帰ってきて国境を越えられるかというプロジェクトをやったりしています。
そのほかにも、ヤフーのオークションで売ったらどうなるかなと思って、出品しました。今は密告ボタンというのがあって、ガイダンスに触れるものがあると、見ている人が通報できるシステムがあるんですが、当時はなくて、それをルイヴィトンのサイトで売るということをしていました。
インターネットでDMをまいて、URLをクリックすると、僕の出品しているヤフーのページが、僕の展覧会場になっているという展覧会です。こうやって値段がついて、いかがわしい写真なんかで出品していたんですが、ルイヴィトンという言葉は一切掲載されていません。あくまでもルイヴィトンというカテゴリーがあったので、そこに出品したということです。結果ですが、ヤフーから強制削除されました。
これは去年ホノルルマラソンに出たときの写真です。太平洋で泳いでいるところの写真です。
これは少し前の作品なんですけど、全身赤い羽根で作ったスーツを着て、首から白い箱を提げて募金活動をしているという作品です。
街頭募金を実際にしたのですが、実際にお金を入れてくれる人がたくさんいて、自給900円くらいになったのですが、赤い羽根共同募金で街頭に立っている人の後ろ側で勝手に、赤い羽根のスーツを着て募金活動を行ったという…。これも、実際に試してみたらどうなるかということを実験するプロジェクトということで行いました。
募金活動の一部始終が映像になっており、その映像の間に赤いスーツを着た僕が、養鶏場で鳥の世話をしたりというシーンが挟まれていて、最終的には募金活動で寄附してもらったお金の中から鳥の餌を飼うという映像作品になっています。
これは去年メキシコの友人の家でプロレスを見て盛り上がって撮った写真です。
今回は造形大学ということで、これは、僕は造形大学の研究生だったときの卒業作品展です。彫刻科だったんですが、マンズー美術館の中でパフォーマンスを行ったもので、透明の箱に入りながらスーツ姿でおめかしをして、会期中4、5日間、箱の中で白い紙を切っては壁に貼っていき、自分が隠れていくという作品です。
当時、僕が考えていたこと、僕がひと言ひと言発言をすれば、それだけ実は自分と人との間に距離というか壁を作ってしまうのではないかということで行っていたパフォーマンスです。
これも、作品というのではないのですが、ちょうど仙台の実家に引っ越すタイミングだったので、当時、ピンクチラシというのが電話ボックスとかにあふれていまして。商売の女の子を呼ぶためのチラシなんですが、それで自分の引っ越し案内を作って、友だちの家に送りつけるということをしました。まとめて郵送するために郵便局に持ち込んだときも、局員の人から「こんな不謹慎なものは送れません」ということで、郵便局と戦った経緯があったり…。そういった経験をしていて、今も昔も変わっていないんだなと感じています。
作品を作るということに対して最近考えていることは、なにか物を作るというよりも、自分が思ったこと、自分はどうやって死んでいくのかなあということばかり最近考えていて、そのときに疑問に思うことを、一つずつ試して、実験していって、このアートという世界はそれを作品にするということを許容してくれるので…。アウトプットする方法として、なにかメディアに落としたりはするんですけれど、基本、「僕はいろいろなことを経験したい」とういところに主軸が置かれています。
- 粟田:
-
非常におもしろいプレゼンだったと思います。1点だけちょっと聞いてみたかったのは、下に展示されている作品では、女性の方がシャッターを押すわけですよね。それはタノさんが、角度を決めるのではなくて彼女たちにシャッターを押させるというのは、どういった意識があるのでしょうか。
- タノ:
-
彼女たちの生活を撮ることはできないんです。それは、彼女たちの生活があるからで。僕がアート作品のために撮ってくださいと言わないのも、僕はアーティストということは言わなくて、ただのお客として入っています。まあ、女装趣味のある人だと多分向こうが判断して協力してくれる。下にある写真も構図がむちゃくちゃだったり、ピントが合ってなかったり、それは、彼女たちの痕跡であり、顔は違うけれど、服装も彼女たちが借りている部屋も、彼女たちのものである。そこが重要だったので、説明して、こういうのをやってくださいではなく、彼女たちとしての仕事をするということは、彼女たちの本質だし、彼女たちの本当の姿を僕は聞きたいから、あくまでもお客として行っているということです。
- 粟田:
-
ありがとうございました。最後は、Mrs.Yukiの二人にお願いします。
- 平嶺:
-
Mrs.Yukiの平嶺と大久保です。よろしくおねがいします。私たちは2006年からユニットを組んでいます。もともと、大久保は、は虫類や昆虫が好きで、私の方は遺伝子の組み合わせによって模様が変化したり形が変化したりという、生命の持っている遺伝情報の形質について興味がありました。
幼い頃からそれぞれ生き物が好きで研究していて、東京造形大学の絵画で学部と大学院6年間ずっと同じ教室で勉強していたのですが、初めて出会ったときから4年間ぐらいは仲のいい関係ではなくて、どちらかといえばお互い毛嫌いしている感じでした。それが、大学院の1年生のときに大久保が初めてニシキヘビのペットを大学に持ってきて、それがきっかけでMrs.Yukiのユニットができてきます。
実は、私はヘビが大の苦手で、周りの友人は触って「すごく気持ちいい」とか言っていたんですけど、二ヶ月ぐらい触れないままだったんです。それが、あるとき大久保から「ヘビの品種にはいろいろな遺伝子があるらしい」と聞いて…。
大久保はどちらかといえば、遺伝形質にはあまり興味がなくて、ナチュラルなヘビの色とか昆虫の色とかにもともと興味があったんですけど、僕はその大久保のひと言によってヘビを触り始め、海外や日本のブリーダーはどうやってこの品種の改良をしているのかというのに興味を持って、ヘビをお互いそれぞれ飼うようになってきました。それが2006年の大学院に入った頃なんですけれども、最初それぞれヘビを飼いながら3年間過ごして、それで2009年に初めて卵が産まれて、ヘビが生まれた瞬間にMrs.Yukiも誕生していきます。
 最初に大久保が持ってきた大学院のペットの名前が、「Yuki」という名前だったので、それをユニット名にして、かつ、お互いのそれぞれ苦手なもの、僕であればヘビであり、彼であれば遺伝の形質の変化で、何か人間が新しい色を作るとか、お互い抵抗があるものが、二人が組むことによって、第三者的な存在のアーティストになれればというので、ミセスというのを付けて。女性の名前なんですけれど、二人とも男だという感じでユニットになっています。
最初に大久保が持ってきた大学院のペットの名前が、「Yuki」という名前だったので、それをユニット名にして、かつ、お互いのそれぞれ苦手なもの、僕であればヘビであり、彼であれば遺伝の形質の変化で、何か人間が新しい色を作るとか、お互い抵抗があるものが、二人が組むことによって、第三者的な存在のアーティストになれればというので、ミセスというのを付けて。女性の名前なんですけれど、二人とも男だという感じでユニットになっています。
今ちょうどスライドに写っているのは、生まれたヘビの個体を明るく照らして、ヘビの色とか、ヘビの生体に関してよく観察できるようなショーウィンドウのようなもので作品を展開しているんですけれども、そういうことから少しずつお互い議論を深めていって、僕らがヘビを純粋にブリーディングして繁殖して育成しているような関係性を作品として立ち上げていかなければいけないんじゃないかということで、人間と生命を表すために、家具の一部にヘビの飼育スペースを組み込んだ展開を始めました。今スライドに写ったソファーの写真が、そうです。
今回下に展示している作品も、Mrs.Yukiの展開なんですが、今年の4月から展覧会が重なって、新作がどんどんできていくんですけれども、その4月の展覧会が、ちょうど粟田大輔さんにキュレーションしていただいた、東京芸術大学の展覧会でした。東京芸術大学の陳列館というところで作品を展開することになって、この今写っているソファーの作品と、次の作品が生まれるんですけれども。ちょうど下に展示しているキャビネットの作品も展開しています。
陳列館という建物自体もすごく古くて、昭和2年頃に建てられた建築で、現代の家具よりもその当時の家具が合うんじゃないかということで、アンティークのフランス製のキャビネットを二人でセレクトして組み合わせていくような展開をとってみたり、そのほかにも、ギャラリーやスペースに合わせて、例えば、ギャラリーが運営しているカフェで使われている椅子を使って作品を展開してみたり。今回、桑沢で展示をするということで、すごく金属質とかシャープなイメージがお互いにあって、ステンレスのハンガーラックの作品を展開しました。
これまで、すごくヘビのイメージがMrs.Yukiの中でも強くあったんですけど、もう少しヘビということではなくて、前回の展覧会からもそうなんですけれど、人間以外の生き物と人間との関係を探るような作品展開をしようということで、今回スマトラオオヒラタクワガタを新作で展開しております。
- 粟田:
-
ありがとうございます。冒頭におっしゃってくれましたけれども、平嶺くんは、小学校のときかから、にわとりのとさかの掛け合わせをやっていたんだよね。それは遊びでやっていたの?
- 平嶺:
-
そうですね。
- 粟田:
-
おじいちゃんがやっていたんだっけ?
- 平嶺:
-
そうですね。うちのおじいさんは、もともと七面鳥とか生き物を飼うのが得意だったのか、そういうこともあって、生物との関係性とかに僕はすごく興味を持って、小学3年生のときに、にわとりの掛け合わせを。
- 粟田:
-
そういうのに元々強い関心があったんだよね。一方で、大久保さんはまた違ったスタンスですけど。Mrs.Yukiはプロジェクトですよね。大久保さんはどういった観点でこのプロジェクトに関わっていますか?
- 大久保:
-
 僕も子どもの頃にやっぱり遊びに行って、ヘビとか虫とか、特には虫類というのがあまりに僕たちと違うというか、理解できない形と生態を持っているということに興味を持って。子どもの頃はそこまで思って惹かれていたわけではないと思うのですが、成長するにつれて謎が深まるばかりというか、これを自分のものにしたいなという気持ちがずっとありました。
僕も子どもの頃にやっぱり遊びに行って、ヘビとか虫とか、特には虫類というのがあまりに僕たちと違うというか、理解できない形と生態を持っているということに興味を持って。子どもの頃はそこまで思って惹かれていたわけではないと思うのですが、成長するにつれて謎が深まるばかりというか、これを自分のものにしたいなという気持ちがずっとありました。
Mrs.Yukiの発想でいったら、ヘビというのはその最たるものだと思うので、念願叶って手に入れたものをみんなに見せたいという思いで、一番僕を嫌っていた人が、価値観が反転してくれたというのが、すごくきっかけというか原動力になりました。
- 粟田:
-
ヘビ皮にも興味があるんだよね。
- 大久保:
-
そうですね。生き物が残したものというか、死体そのものでもいいんですけれど、ヘビの形というか、生態によって残ったものそのものに対する興味。僕、絵を描いてきたんですが、平面を書いているうちに生まれてきたむくわれなさ、僕だけがこねくりまわしているような、それが全く返ってこないようなその思いが、だんだん気持ちよくなってきて…。
そういう風に届かないからこそ、動き続けていられるなという、勘違いしたままでも動き続けられるなという思いを、標本とか、抜け殻とかにそのままアプローチし続ける、触り続けるような作品をこのプロジェクトの中で作ったりしています。
- 粟田:
-
ありがとうございます。母袋先生からいただいた「CSPに寄せて」という文章にあったように、純粋視覚を超えた食の問題とかね、生物、生態系、時間に対する問題なんかを特に掲げた展覧会なので、それぞれの作家がどういう形で今回の展覧会に向き合ったのかということが、非常によくわかっていただけたのではないかと思います。
第二部では、今回のタイトルである「他の文脈に、たべられるという事について」、軽い感じで話してみたいと思います。
- 粟田:
-
シンポジウムのタイトルにある、辻さんの話にいく前に、それぞれ今回の展覧会についてもう少しコメントをし合ったほうがいいのかなということで、末永さんから、今回の展覧会のコメントをお願いします。あとは、自由にぼくに振られなくても自由に発言していただければと思います。
- 末永:
-
なんとなく話し始めますけれど、今回の展覧会にどういうメンバーが集まったかというと、アトリエの中で完結するものを作るというよりは、多分、環境とか、対「人」だったり、自分以外のなにかに向けて反応を期待して投げかけて、そこからのフィードバックを元に、なにかを作り続けている人たちに声をかけたつもりでいたんですよ。それが展覧会という形にどうまとまるかなと思っていたんですけれど、表面的に共通点を見いだせるのではなく、思った以上に根底のところで共通点を感じとれるようなもの、そういうショーにできたんじゃないかなと思います。
そういう意図を展示前に説明できたのかどうか不安があったのですが、今回の展覧会に向けて、どういう気持ちで迎えていただいたのかなというのをそれぞれ聞きたいと思います。Mrs.Yukiのお二人、お願いします。
- 平嶺:
-
「場への働きかけ」というテーマがあったときに、場といってもいろいろ、作家からすると、展覧会場での桑沢のこの場所であったりとか、今までやってきた展覧会場、作品が展示される場所というのももちろんあるんですけれども、もうちょっと大きく捉えたときに、ジャンルですよね。それぞれの絵画だったり、彫刻なのかインスタレーションなのかちょっとわからない部分もあるんですけど、それ以外の例えば、は虫類という生き物のジャンルであったり、大畑さんであれば、「食べる」ということだったり…。実は掘り返すとすごくバラエティー豊かなのに、空間的には、すごく落ち着いた感じでまとまっているなというか。最初思っていたよりは本当にしっくりくるような展覧会構成にはなったのではないかなと思います。率直な印象です。
- 大畑:
-
空間としては、誰かの家に行ったかのような、そういうものになったんじゃないかなと僕は思っています。実は僕も、展覧会という中で作品を見られる場所、見る人が一番フラットに見られる場所って自分の家なんじゃないかなってよく思うことがあるんですが、この空間自体がアスファルトであったりとか、壁がパンチングだったりしていて、がらんとしていたときは、誰もが嫌がった空間で、僕もさすがに初めて見たときは躊躇したんですが、それが驚くほどいい感じでできたんじゃないかと思いました。
Mrs.Yukiとか狩野さんとか、タイガさん、末永さんに関しては作品は知っていたんですが、今回一番の発見は末永さんで。「絵が空間を変える」という感覚を今回味わったというか。逆にタノさんの作品は、写真の中に密度があるものなので、場を変える力を写真自体が持っているんですけれど、それとは違って、絵というものが空間を変えていく場を、今回見られてよかったと思いました。
- 狩野:
-
僕も多分同じような印象になるかもしれませんが、やっぱりグループ展って、誰か「こういう展示構成にしたい」というビジョンを持ってきていて、それに参加する作家は、そのビジョンとテーマから求められているものの中でどうやって外していくか、というのがおもしろいところだと思うんですけれども。
場への働きかけって、すごくなんでも含みうる広い言葉なので、最初に「出品しませんか?」と言われたときに、すごくストレートに受け止めて、もしかしたら現場で作るインスタレーションを期待されているのかなってなんとなく思ったんですけど。
展示空間を見て、それが最適ではないかもしれないと思って、そのまま様子を静観していたら、なんとなく今展示している場所の配置までは出てきたんだけれども、誰がどこに作品をいくつ置いて、どこを作品が切り替わるラインにしましょうというのって、結局設営まで曖昧なまま進んでいた割には、展覧会全体のビジュアル的破綻がないというのは、多分他の作家のみなさんの場数というか、場に対する柔軟さみたいなものが発揮されたのかなと思いました。中にはこういうことが興味の対象にない作家さんも、善し悪しではないのですが、いると思うので、それがすごく印象的でした。
- タノ:
-
僕もみなさんと同じなんですけれども、僕、遅れて1日目に入ったら、もうMrs.Yukiは展示が終わっていて、あと辻君も終わっていて、その場を読み解きながらどれくらいの距離感でどういうふうに置いたらいいのかというのを、なんだかんだ言って、みんな意識できる人たちだったので、「すごいな、みんな」って僕は思っていました。
今回呼んでいただいたときも、同じような世代、時間を過ごした人たちで、僕も作品はそれぞれ知っていたので、逆に「僕なんかはまずいんじゃない?」というのを相談させてもらったんですけれど。実際は、あの作品じゃないオファーが最初あったんですけれど、僕的にも、あの作品は今まで美術館では展示したことがなく、どこか小さなギャラリースペースだったり、それこそ、南の島の空き家みたいなところでしたり、そういう空気感というんですか、いわゆるホワイトキューブとか、お膳立てされたところではないほうが、作品を置くというときにマッチングしているんじゃないかと思ったときもあったし、継続的に行っている作品ではあったので、迷ったんですけど…。やってみたら思いのほか良かったんじゃないかなというのが、正直な感想です。
- 粟田:
-
今回の展覧会は、造形大学の実行委員があって、割と自主企画展の要素が強いと思うんです。自主企画という展覧会は、60年代、70年代の作家はかなりやってきているんだと思うのですが、どうでしょうか。みなさんいろいろな展覧会を今までやってきていると思うのですが、展覧会というとどうしてもなにかを発表する場であると同時に、すごく消費主義的に消費されていく場でもある。例えばアートプロジェクトなんかも、もちろん行政の地域活性化のためのなにか、というような形として、大きい枠組みでいうと消費されるという側面も少なからずあると思うんですよ。
みなさんにとって展覧会、アートプロジェクトでもいいんですけれど、どういうふうに位置付けているのかなというのをなんとなく話し合えればいいかなと思うんだけど。
平嶺さんは、甑島のアートプロジェクトを企画していて、10年目で一区切りを迎えたわけだけど、何がきっかけで始まったんですか?
- 平嶺:
-
2004年から、学部の3年生のときですが、夏の一ヶ月間、私の故郷である鹿児島の甑島というところに、学生とか若手アーティストとかに声をかけて空き家に滞在してもらい、作品を制作するというプログラムをここ10年間ずっとやってきたんですけれど。
始めたきっかけは、私が先ほど話したことと全く一緒なんですけれど、人間の持っているDNAの中の表現形質が、作品としてどういうふうに出ているのかなということに興味があって。アーティストのお父さん、お母さんの職業だったり、おじいちゃん、おばあちゃんはどういう癖があるのかなとか、そういうのを聞きながら、この作品おもしろいな、この作家おもしろいなというので、この作家たちがホワイトキューブではない場所で発表するなど、制作環境が変わると、どういう変化が見られるのだろうという、ちょっとした実験のプロジェクトだったんです。
それがきっかけで集まっているんですけれど、周りから見れば、高校がないような島なので、若い子が来て町を元気にしてくれているみたいな別の認識があったうえで、市から補助をもらうようになったりしました。
アーティストにとっては、もちろん自分の作品の制作なので、自分が経験したことのない暑さの中で作品を作ることで、何かを見いだす作家もいれば、そういうのを見ていた島の若い人たちが、もっと「自分たちの表現とか生き方ってなんだろう」って発見していったということもありました。
それで、ちょうど10年目、その前ですね8年目くらいから、地域の人たちが自分たちでプロジェクトを始めたんですよ。そういう動きが出てきたので、僕はもともとアーティストに興味があったんですけど、地域の人たちが自分で生き方みたいなのを考えて動き始めたというのは僕の中で成果で。
役所からしてみれば、どんどん続けて、どんどん発展させて、直島とか越後妻有のようになって、もっと観光客を呼んでほしいみたいなのも期待としてあったと思うんですけど、僕としてはこのスタイルの基盤がある程度島にできて成長してきているので、区切りを今回10年目ということで考えました。
- 狩野:
-
参加してもらった他の作家さんとか、島の人に対する影響はわかったんですけど、そのプロジェクトを自分でやることは、平嶺くんの制作とってどういう位置づけだったの?
- 平嶺:
-
僕が大学に入って1年目のとき、周りのおもしろい学生たちと比べて、自分の絵画表現に対する限界を感じてしまっていて…。自分の絵画表現も、島をテーマにした作品だったり、ひたすら方言を書き続ける絵だったりとか。それに泥臭ささを感じてしまって、「自分のアイデンティティを、他のアーティストたちに掘り起こしてもらったら自分にとってどうなるんだろう」という。その結果が、Mrs.Yukiの流れになっているのかな。自分の制作の中で、個人でも制作をしているので、年を重ねるごとに吸収できているかなと思います。
- 狩野:
-
僕の場合は、自分はあまりたくさんのことを同時にできないタイプなので、例えばプロジェクト運営と制作を同時にやらなきゃいけないこともあるけど、それは自分にとっては良くなくて、今話を聞いて、それが自分の制作を一歩前に進めるために必要だったというのがわかりました。
- 平嶺:
-
でも、基本的に僕は運営はあまりやっていないんですよ。親戚中でやっているので。姉に会計やらせたり…。いろいろな人を巻き込んでやっているんです。
- 狩野:
-
それは自主運営の企画というよりは、自分の制作環境も含めてサポートしてもらえるような状況を作ったみたいな。すばらしいですね。
- 粟田:
-
今のに対して何かコメントありますか? タノさんとかはそういうプロジェクトにいろいろ関わられていると思うのですが。
- タノ:
-
僕もいろいろなNPOとかから声をかけていただいて、学校に滞在するプログラムとかもいくつかやっています。それこそ、僻地の小学校とかに行って、1、2週間滞在して子どもたちとなにか作るとか。あとは島に滞在して、その土地のどうにかしてほしいみたいなことに関わったりとか。参加する側、呼ばれる側として。
一方で、僕自身も仙台で、「たまにわ(霊庭)」というフリーペーパーを作っていました。それは、仙台に帰ったときに、仙台で活動をしている作家もいっぱいいるんですけど、「仙台にはギャラリーがないから発表する場がないんだよね」みたいなことを、みんながみんな口を揃えて言っているんです。「仙台は遅れている。なぜならばギャラリーがないから」みたいな。
僕はそれはクリエイティブじゃないなと思って。フリーペーパーって普通、消費されるもので、広告があって、いっとき見たら捨てられるものなんですが、これは、画集のようなフリーペーパー、作品の写真とテキスト、タイトルとそれだけ。広告は、スポンサーのバナーが最終ページに入っているくらい。それを自分で企画運営していました。場がないなら場を作るべき。結果、3年で訳あってやめたんですけど、始めるときは「5年だな、長くて」と思いながらやっていました。
呼ばれるときも、企画者とよくけんかになるんですが、これはどういう継続性、長・中期プランでどういうふうにプロジェクトをやっているんだ、ということにひっかかることが多くて。
平嶺くんは、10年というのは最初から決めていたのですか?
- 平嶺:
-
そうですね。20歳のときに、10年後に甑島の中で橋がかかるということになって。島って、タノさんもよく知っていると思うんですけど、地域ごとのライバル意識がすごい強いじゃないですか。でもそれが橋がかかった瞬間にどうなってしまうんだろうと思って。
橋がかかる前に、アートプロジェクトを集落でやりながら、自分たちが昔得た情報、昔あった争いごととか、良いも悪いもそういう情報をやんわりしたいなあというので、なんとなくやっていたんです。
結果、自民党が負けて民主党になったときに、工事自体も納期が遅くなってしまって、あと5、6年かかるようなんですが。それまでプロジェクトを継続させるべきなのか、島の人たちがどんどんやりたいプロジェクトができてくる中で、アートじゃなくても、地域から発生したプロジェクトがあるから、僕はそちらのほうをすすめたんです。こちらはこちらで、東京でなにか新しくプロジェクトをできないかというふうに。
- タノ:
-
僕も、参加するときも自分で企画するときもそうなんですけど、すごく彫刻的な考えなのかもしれないけど、始める瞬間に終わりのビジョンをなんとなく持っていないと、なあなあで進めていき、なんとなくふわーっと消費されて、それを運営する側が、お金がどうだ、食えるかどうかみたいのが多々見受けられて。頑張って1年やったのに、次の年にはその話自体やNPOが消滅するなんてことも結構あったりして。もちろん運営するのは大変で、自分でフリーペーパーやっていたときは、スポンサー集めがうまくいかないときは自分で持ち出したりしていたので大変なのはわかるんですけど、そういったトータルなビジョンがないのに、ただの権利主張ばかりで、自分が何をすべきなのかという義務を果たせていない…というのがよくありました。
- 粟田:
-
そうですね。だから60年代、70年代。特に70年代かな。自主企画が流行ったのは。ゼロックスコピーができたりとか、映像のカメラとかが割と入手できるようになった時代だから、行かなかった人にも後から自費出版で記録集とかを出して見てもらえるとか。
今はインターネットやソーシャルネットワークがあるので、多分、いろいろなことができる可能性があると思うんですよね。タノさんが言ったように、ある種自分で限界、どこまで問題設定、どこまで閉じるかということを考えながらやるというのは、聞いていて非常に重要な意見だなと思いました。
僕も自分で今、「comos-tv」という、あまりまだ動かせていないですけれど、ユーストリームを使ってアートの番組みたいなのをやっているんですけど、タノさんが言ったことをもう一度考えながら運営したいなと思いました。
ここからは、辻さんの「自分のつくったものが、他の文脈にたべられるという事について」というメッセージを受けて話したいと思いますが、みなさんどいう印象ですか? 大畑さんとか、どうですか?
- 大畑:
-
正直、消費されるというのは前提な気がしていて、僕の中ではそんなに興味の対象ではないんです。作っているものも、チョコレートに火を付けるという作品なんですけど、イベントをしていると「パティシエですか?」とか聞かれることがあって、単純にうれしいんですね。
自分にとってはアートの活動の一つだと思っているので、「彫刻家です」というと、よく馬鹿にされて「チョコク家ですか?」みたいなことを言われたりすることもあるんです。でも、なにか別のジャンルに横断したときに、そのジャンルを超えたものを提供するのが重要だと思っていて、逆にそれができないとアートとはいえないんじゃないかなと思います。
火を食べるということは、普通の料理人はやれないので、アートという前提を付けることで納得させられるという意味では、すごくいい場所だなと考えています。
- 粟田:
-
実際に僕はまだ体験していないですけど、下の展示とか見ると、ちょっと儀式的な感じにも見えるんですけど、そういう意図なんかもありますか?
- 大畑:
-
やはり火を食べるために来てもらうので、それだけのためのこちらの準備というか、それはすごく大切だと思っています。
- 粟田:
-
音楽とかが入っているのは、そういう文脈も…。
- 大畑:
-
はい。
- 粟田:
-
末永さんはカレンダーとかすごくおもしろいものを作っていると思うんですが、今までの話を受けてどういうふうに考えていますか?
- 末永:
-
カレンダーは、これまで3年間作って、結構評判よくてうれしいんですけど。本職のデザイナーさんにできないことだなと思っていて。僕はデザイナーとして生計を立てていないので、アーティストという立場だから作れることがあり、大畑さんもパティシエとして生計を立てていないからこれができるということもあり…。経済活動と切り離せているからこそ、介入できる余地があるのかなという気がしています。
- 大畑:
-
それがなかなか理解されないことがあって。チョコレートの技術が上がると、今度は、「こんなこと作れない?」と言われたりするんですよね。これは自分でやりたいからやっているんであって、そこのズレというのがまたおもしろいなと思っているんですけどね。
- 栗田:
-
いろいろな話が降って沸いてくると思うので、それはタノさんが言っていた、限界を自分の中で作ってそこをどうコントロールするのか?ということにつながってきますよね。
Mrs.Yukiはヘビの…。そこはあんまり話してもおもしろくないかもしれないけど…。
- 平嶺:
-
おもしろくなかったらやめます(笑)。そうですね。この前の展覧会のときに初めて、年間7万匹のゴールデンパイソンを見ている、横浜のペットショップの店長をお呼びして、トークショーでいろいろ話したんです。
は虫類業界からしても、自分たちが作ってきた業界がアートと関われるということ自体が、すごく華やかというか。今まで暗闇の中でブラックライトをたいて生き物と…という感じだったのが、もっと明るい生態に対する興味とか、多くの人がタッチしやすくなるような展開をしてもらってうれしい、というようなことを言ってくれました。別のジャンルのものと、自分たちの表現を組み合わせたときに生まれてくる、領域が重なった部分、ふくれてくる部分は、自分たちがいたからできた領域だと思うと、すごくアート的というか。
- 狩野:
-
専門家じゃないからできることはあると思うし。特に、動物の話は自分の作品で関わりがあるので、Mrs.Yukiの作品を見ていて思うところがありました。ペットショップのブリーダーの方とかは、専門業界の中でもごく近いところにいる人だと思うんですが、一歩外に出て動物園業界、動物の飼育展示のプロフェッショナルの人からすると、動物が見えない可能性がある展示とか、管理が合理的にできない展示というのは、まずセオリーから外れるし、さらに、よりアカデミックな生物学のところとかに行くと、学問上重要な問題とそうでもない問題があって。
僕自身、生物学の専門家じゃなくて単なる趣味で本を読んでいるぐらいでしかないけど、例えば、ムクドリがリンゴといっても、「ふじ」とか「ジョナゴールド」とか、「ゴールデンデリシャス」とかいろいろあるけれど、どの品種が好きかということは、観察すればわかることかもしれないけど、学問上はそんなに重要ではない問題なんですよね。生物学の専門家では、研究者としてはその問題を主に扱っている人は存在することが難しくて、それをアーティストが自分の問題として設定して考えてみることはできる。
自分が建築系の専攻から、ファインアートの方で発表しようと思ったきっかけにもつながるんだけど、建築家ではなくてアーティストになって空間に向きあうと、不便な空間とか合理的じゃない空間を設計することもできるし、同時に生物学では重要ではない分野を扱うこともできる。専門家ではできないことをやるということと、アーティストである自分との関係って意外とみなさん共通しているところがあるんだなと思いました。
- タノ:
-
僕の場合は、それに当てはまるかわからないですけど、ある意味、彫刻的なものを作っているんですが、今回の「15min.ポートレート」のようなものは、僕は写真家ではないからこそ、カメラを人に渡して撮り、できあがったものの構図はある程度気にしますけど、ブレていることも含めてそれで良しとする。一つの写真作品を作るわけではないことをできるのは、ある意味彫刻家というところにいるけれど、他のところに手を伸ばしてやるということにつながるのかなと、ちょっと聞きながら思いました。
- 栗田:
-
かといって技術を軽視しているわけではなくて、技術を別の形に使うとか、使われていないところの技術を発見するとか…。そういうところもあるのかなと思いました。
タノさんがおっしゃったように、もちろん政治的な問題もあると思いますし、ああいう場所自体を撮影する写真集は、ないことはないと思うのですが、タノさんがやられているような、あそこでその人に渡して撮ってもらうということが重要なんだな、と分かりました。
- タノ:
-
実際、僕の中ですごく継続したいと思ってやっている理由の一つには、カメラというものを、写真作品を作るための道具というよりも、今まで一眼レフの大きいカメラを持ったことのない世界観で生きている人が、それを持って写真を撮るときのコミュニケーションのツールとして、カメラや写真が効いているなとすごくやりながら思っています。これは、10年、20年前だったらもしかしたらこの写真はできていないかもしれなかった。
今は、プレビューできるので、どううまくとれたかとか、撮った場で見て確認しながら構図を変えてみたり、手をグーにしていたのをもうちょっと指先を延ばしてと言われたり、確認作業として使われているのが、デジタルカメラというものが主流になっている時代がきたからこそ、できることなんだろうなというのは思っています。
- 栗田:
-
70年代の写真、多分映像とか写真も、美術家たちが好んでやったのは、ああいう道具をどうやって使ってどういうふうな別なことをしようかということでした。そこで、自主企画展みたいなのが行われていたという側面があると思うので、そういう問題が2回転目にきているのかなと印象が、外から見ていてあるのですが。
大久保さんはどうですか? ちょっと戻ってしまうんですけど、さっきの専門家ではないからできることとか、そのあたりのことはいかがでしょうか?
- 大久保:
-
僕たちが今下で飼っているヘビというのは、ゴールドパイソンという品種で、ブリーダーの世界で進んでいらっしゃる方の中では、あまり価値としては高くないというか、お金でいうとそこまでのものではないんです。
僕にとっては、ヘビと出会うこと、飼育すること、なぜ僕たちはペットとしておさめるのか、僕たちが勝手に品種を改良したりしているというのはどういうことなのかということに興味があって。もしかしたら、人間の勝手なエゴではなくて、むしろ野生に住むヘビたちが、その色彩とか形態で、僕たちをおびきよせているというか、人間の方がそそのかされているのではないかと…。
そうだとしたときに、必ずしもあそこで飼われているヘビは、人間の都合で飼われているわけではなくって、とらえられることによって、僕たちをだまして、あそこにいれば温度も快適に保ってもらえるわけだし、餌も定期的にもらえるわけで。そういう関係が価値観になっていったらいいなと思っています。
- 末永:
-
Mrs.Yukiの作品を発表する場としての、今は、美術のフィールドだけど、Mrs.Yukiとしてベストなのはどこかなというのを僕は感じていて。例えば大畑さんは、展示空間よりも、パフォーマンスをやる場所をどう作るのかということを積極的に考えているような気がするんだけど、Mrs.Yukiは、どういうのがベストだと考えているのかな?
- 大久保:
-
作品を発表する場所というのは、僕だけで言うと、ほぼショールームに近いような感じで、人の家庭の中にヘビがレイアウトされているのではなくて、結合されている状態が理想。そういう風になっていったらいいなと思っているので。
- 狩野:
-
それを現代美術の空間で見せるのか、もしかしたらインテリアショップかもしれないし、ペットショプかもしれないしということですよね。美術の場で発表するのが大事なのかどうか…?
- 平嶺:
-
それこそ今回の狩野さんのように、鳥を飛ばさず、彫刻として扱う見せ方と同じように、どこがベストとかではなくて、僕らはそこになにを落とすかという感じでいるような気がして。
今、展覧会が連続して美術館とかアートの空間が多かったんですけれども、僕らはそこの場所を与えられたら、そこでヘビが飼育されたり、クワガタが飼育されたり、生き物が存在するような空間や、生き物と人間の関係をどういうふうに提示できるかを考えるので、家具との組み合わせも、今年の春の展覧会で本格的に動いてきたというのがあって。ここがベストというのは、二人とも今はまだなくって、しっかり応えられていけばいいのかなと思っています。
- 栗田:
-
僕はやっぱりタノさんのあれにこだわっちゃうんだけど、彼女が写真のシャッターを押すという素人性が重要なのではなくて、ある意味、演劇性に近いのかなと思うんですけど、タノさんとの関係性の中で押させるという…。
狩野さんの発言を聞いてちょっと思い出したのが、今、ロボット演劇というのがやられていて、簡単に言うと、技術者が開発したロボットを使って、平田オリザさんが演出するんですけど、ロボット技術者と演出家のアウトプットとか、問題設定とかが全然違うんですよね。どちらが良い悪いではなく。やっぱり平田オリザはロボットを作ることは素人だけど、演出家としては巧みな技術を持っている。そこに入ることによって、違う問題というか、より考えさせるものがあるなという意味で、タノさんの写真もある種、演劇的な空間が立ち上がっているのかなというのをすごく想像してしまいました。
- 狩野:
-
ロボット演劇で平田さんが演出家ではなくて、ロボットの方に少しでも踏み出しすぎてしまったら、専門業界で素人がしたみたいな仕事になってしまうという。タノさんも、自分がどこで発表するかというのはしっかり選んでいて、これは、良い悪いの話ではなくて、タノさんの作品はニコンサロンで発表されることはないな…。もしあったら、ごめんなさい。まあ、あってもいいんですけど、今のところ多分ないと思うんです。
末永さんも、平面作品を日本の東京でいうと、清澄方面か上野方面で発表するのか、銀座方面で発表するのか、多分、選んでいるんですよね。上野方面でも、なんとか会なのか、なんとか展なのか、いろいろ選択肢があるわけだから。それが「たべられる事」と関係あるのかな…。
消費される場所を自分で選ぶということ。消費というと終わっちゃったみたいな感じだと思うけど、どういう文脈で、どういう人に見られて、どうなるかというのって、みんな選んでいると思うんですよね。
- タノ:
-
僕の写真に関しては、見せたい場所というのは、自分のカメラの中なんです。自分の経験をするための一つの行為で、次にそれを広げることもあるわけですけど、それが決して、いわゆる美術館的なショーにするよりも、本だったり写真集ということも念頭に置いていて。
実は「15min.ポートレート」も、僕の中には拡張の方法もあるから、彼女たちと過ごした時間の中で話した内容をテキストにしていて、「こういう事象があった」ということを残したいという。それを美術館というところで体験して帰るのもいいのかもしれないけど、歴史書じゃないけど、この国であった出来事として残すこともありなのかなと考えていました。
- 栗田:
-
大畑さんは、音楽家と一緒に場を作っていくというあたりで、どういったやりとりを考えていますか?
- 大畑:
-
結局、僕の場合はモノからスタートしている。モノに対する疑問があって、なんでモノがあるのかとか、そういう問いから出発しているんですけど、それを見せる時に、どういう問題にぶつかるのかなと言うと、最終的に作り手だけでは成立しない事なんですよね。
彫刻では、よく台座の問題が取り上げられますけど、台の上に載せられていることで作品ということが担保になっているのか?、台自体が作品なのか、あるいは、そこに置かれているものが作品かは、見ている人が決めるのか?
こうした問いに対して僕は、鑑賞者に最終的な判断を委ねたいと言う思いがあって、鑑賞者の手というものを作品の台座に据える事を考えています。その為、僕の作品は手に取ることが出来るサイズというルールを自分の中で与えています。見ている時には、そこにチョコレートという物体が作品として現れているんですけど、鑑賞者がチョコレートを手に取る段階で作品を支えているものが作り手から鑑賞者へと移ると考えています。そして食べる時には、鑑賞者自体が見られる側になります。その時に重要なのは、鑑賞者は自分の意思で手に取って口にしている事です。これは作品に積極的な関わりが生まれる仕掛けを僕なりに工夫しているつもりなんです。同時に、見る人と見られる人の関係が刻々と変化していくという状況を作れたとき、言葉ではうまく言い表せないんですけど、一体感みたいなのが生まれたら、僕としてはそれが作品として成立していると考えています。
話が脱線してきていますが、食べ物を作品として扱っているーのは、自分の作ったものが誰かの体の中に入るというのが、すごくワクワクするんですよね。僕の場合、石や木で彫刻を作っているときとは緊張感が違う。成分や、衛生面、あらゆることを気にして作らなければいけない。こうしたこだわりを持って作る事は、僕にとって重要です。
- 栗田:
-
みなさんはご覧になっていないかもしれないけど、今、東京現代美術館で90年を振り返る常設展をやっています。それとは別に、年次展を毎年やっていて、1999年に「ひそやかなラディカリズム」という展覧会があったんです。70年代的な学生運動みたいなことではない、別のラディカリズムというのを提示していて、特に狩野さんや大畑さんとか見ると、そういう文脈をある意味で引き継いでいるのかなと思ったんですが…。ご覧になっていないですよね?
- 大畑:
-
見ました。覚えています。
- 狩野:
-
僕は見たけど中学生でした。
- 栗田:
-
縦のラインをあえて今説明してみたんですけど、話を聞いていると、そういうのも関連しているのかな。
- 大畑:
-
音楽が関わってくるという話でいうと、一つのものを見せるのに、場をどうやって作るか、と考えたときに、どんな場所でもなにか切り替える装置が必要だなと思って、その中に「音楽」という選択肢が僕の中であって。彼自身、蜷川幸雄さんとか、いろいろな舞台の音楽を作っているということもあって、僕の要求していることにかなり応えてくれるんです。そういう意味では、作品のベースは僕にあるんですけど、そのときのイベントの流れとか構成とかは、彼と詰めているところがかなりあります。
- 栗田:
-
時間が5時を過ぎましたね。なにか言い足りないこととかありますか?
- タノ:
-
打ち合わせのときに話していたことなんですけど、「他の文脈にたべられるという事について」。僕は文脈を主文ととらえるか、それとも作品の鑑賞者の意味とか理解ととらえるかは、分かれると思うんですけど、どちらにしても食べられてもいいという気持ちがあって、食べられようが食べられまいが、「食べられてるな」と思えば、自分はそこで毒になればいいし。
ものを作るということは、そういうことをやっていくことなんじゃないかなとなんとなく、思いました。この中でやりなさいではなくて、そこから出る瞬間の爆発力が意味があるわけで、世の中が厳しくなろうが、がんじがらめになろうが、一個人としては、そのルールがおかしいというのではなく、自分で責任をとって自分でやるという、それだけしかないんじゃないかなというふうには思っています。
- 末永:
-
逆にいうと、ここにいる人たちは食べられるということに対して、意識的な人しか集まっていないと思うので、そういうことなんだなとは思います。
- 平嶺:
-
作家活動もそうなんですけど、ちょっと話がずれるのですが、ギャラリーに勤めていることもあって、いつのまにか、他のジャンルに関わっている可能性もあるなというか。コレクターさんと言っても、個人もいれば企業もいたりして、個人であれば、作品を購入する目的も、家がビル街の中にあって窓がないから、壮大な空間を演出したりして、生活リズムができたりとか、企業であれば、チョコレートの品質を上げるためのインスピレーションのためにこの作品がほしいとか。設置まで行くんですけど、それに準ずる作品とか関連する作品が陳列されたりしているので、自分が思っていないところに作品のポテンシャルがあって、社会や個人のために生かしているんだなと実感していることが多いくて。なんか、アートっていいなと思います。
- タノ:
-
僕の写真を見ながら笑っている集団がいたりとか、さっき見に行ったときもそうだったのですが、笑われることも、おっさんの汚いコスプレ写真みたいに取られることも、受ける側の経験とか理解にゆだねるしかないのは当たり前で、「この作品はこれこれこうで、この島の問題点は…」みたいなのは、こういう場ではしゃべりますけど、たいして重要なことではなくて。
作品とか美術の行為って、決して瞬間で終わるものではなくって、自分が若い頃に接した作品が、年をとっていろいろな経験を積んだときに、ものすごくおもしろく見えたりすることってあると思うんです。僕の作品も、例えば若い男性がそういうところに行き始めて、そういうところの女性とのやりとりの中で何か感じるものがあったときに、作品の向こう側に見えるものがあるかもしれない。
それでもいいと思っていて、彼らの文脈に自由に食べられてほしいというのがある。食べられることは嫌だとかそういうのはないなと当初から感じていました。
- 栗田:
-
まとめていただいて、ありがとうございます。今話していて、思い出しました。梶井基次郎という小説家なんですが、もう100年以上前の作品かな。「檸檬」という小説で、丸善に檸檬をひっそり置いて、確か爆弾だと自分の中で思って置いて帰っていくという。それを思い出して、家に帰って読もうと思いました。
- 末永:
-
自分に関して言うと、食べられるほどアートシーンに関われていないので。消費という意味では、作品の売買でいう世界の大きなアートシーンからは、完全に切れているという自覚はあるんですよ。ただ、自分が関われることの中で、作ったものを見てくれる人がいたり、足を止めてくれる人がいるという関係自体は、決して重要ではないということはないと思うので、そこにしっかり向き合って、ちゃんと作品という形で残していければ…。見てくれる人が必ずいるんだということを信じていくだけかな、という気はしています。
- 狩野:
-
レモンの話は、すごくリアリティがありました。
- 栗田:
-
一応これで締めましょう。会場の方でご質問があれば。このあと6時からレセプションがあって、作家の方もいらっしゃるので話せると思うのですが、この場で質問されたい方はいますか? 母袋先生、これで終わりにしていいですか?
- 母袋:
-
もう少し、質疑応答があれば、なおのこと理想かな。
- 栗田:
-
1分待ちましょう。ないかな。母袋先生なにか言うことないですか?
- 質問者:
-
東京造形大学の有吉です。すごくレベルの高いシンポジウムだったんじゃないかなと思って、聞いていました。
大畑さんが、自分の作品が誰かに食べられるというのがワクワクするというのが、すごくキーワードになっているんじゃないかと思って。自分の作ったものが誰に消費されるかというベクトルと、誰に食べられたいのか、どこに食べられたいのか。そこら辺はどうなのかな?
アートが、他の文脈にどういうふうにリンクしていくことができるのか。そういう視点が、むしろこれからを作っていくんじゃないかなと思って。みなさんがどういうところにリンクしていくのか、ここに宣言していただきたいと。
- タノ:
-
僕は、どこにというよりもそれは、そうですね。自分と近しい人から少しずつ広がる感じ。昔は世界平和というか、地球の裏側のことを一緒になって悩んだりしていたんだけど、地元が震災でボランティア活動やったり、バックパックで地球一周旅行したりする中で、裏側のことは自分がどうこうできるのではなく、自分と一緒に生活している人たちがどう、なにを考えていくかということ、それをちゃんと自分の言葉で自分の考えで伝えなければいけないし、その人たちも自分のフィルターを通して伝えていく。そうしたときに、初めて裏側に行ったときに意味をなすのではないかな。
作品を見に来てくれるお客さんを無視するわけではないけれども、僕が作品を作るということは、身近な人たちにどう良くも悪くも影響できるか、そこに尽きると宣言します。
- 大畑:
-
僕の場合は、美術業界とか美術の世界にもう一度近づきたいというのがありまして、最後に自分が思っている言葉が伝わる人たちというのは、多分そこにいるんですよね。そこにいる人たちがもう少しお金をちゃんと用意してほしい。僕もいろいろなイベントに声がかかるんですけど、人もお金もかかるので、コスト面で理解を得られないことが多いので…。
でもやりたいということを叶えるためには、自分自身が今やっていることの中で、お金を作り出していく動きというのは、まだ悩んでいるけど、必要だなと思っています。なので、美術業界に接近したいと僕は宣言します。
- 狩野:
-
僕の場合は、自分の立ち位置が常にぷらぷらしていて、ものを作ったりするときに、極端に言うと全く逆の二方向から物事を考えているというのは、力になっているので、そのスタンスは変えないようにしつつ…。現状、つい最近気にしている問題としては、動物のことを想像するうえで、動物の飼育とか生物の特性とかからはある程度考えたので、最近、狩猟免許をとってハンティングですね。動物を捕らえる方の技術とか、知識というものが動物からどういうふうに認識されているのかみたいな。別にハンターになりたいというわけではないですけど。最近気にしている問題はそんな感じです。
- 末永:
-
さっき、若干ネガティブなことを言ったのですが、そうはいっても、自分と同世代プラス10ぐらいで、日本に限らず、世界中にいいペインターがいるというのは実感していて、そういう人たちとつながれたらいいなというのは、思っています。そういう人たちの作品を見たりすることが楽しいので、本当に喜びを感じていますね。
- 平嶺:
-
Mrs.Yukiでは、今まで自分たちが繁殖させてきた個体を展示しているんですけれど、それ以外にも購入して、これから繁殖させるというのがあるんですが。ブリーダーが世界中にいるので、ブリーダーと一緒になにかやってみたいとか。
あと、これまでもやろうと思っていたのですが、今回ハンガーラックの作品で服をかけているんですけど、そういうファッションの世界と組んで、ポテンシャルを持った作家となにかやったり、企業と組んだり、Mrs.Yukiも、こうして二人である人物像を作ろうとしているので、もっと多くのつながれる人と関係を持って、アートというところに業界を引き込むような関係性を作れたらいいなと思っています。頑張ります。
- 栗田:
-
よろしいですかね。みなさん、長い時間ありがとうございました。
●第二部