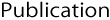CSP4 シンポジウム
- 藤井:
- みなさま、本日はシンポジウムにお越しいただきまして、ありがとうございます。東京造形大学の藤井匡と申します。
このシンポジウムは、東京造形大学付属美術館で開催中の展覧会「CSP4 あること ないこと」の関連イベントとして開催するものです。この展覧会は東京造形大学を卒業したアーティストの活動を紹介するために行われているもので、2013年から毎年開催しており、今回で4回目となります。過去3回は渋谷の桑沢デザイン研究所で開催していましたが、今回からは大学付属美術館に会場を移しての開催となります。
最初に、東京造形大学付属美術館館長の中里和人より、みなさまにご挨拶いたします。
- 中里:
-
みなさま、こんにちは。本日は「CSP4 あること ないこと」にご来場いただき、ありがとうございます。館長の中里です。美術学科の絵画と、彫刻専攻の教員が中心となって、東京造形大学卒業の作家を招待するCSPも、今回で4度目を迎えることになりました。そして初めて、付属美術館で開催する運びとなりました。ここに至るにあたっては、美術学科の先生方のご尽力、大変なものと感謝をしております。そして、この活動が継続されて造形大学の芸術者教育に厚みが増し、今後も、積み重なって行くことを期待しております。このあとはシンポジウムが開かれるのですが、このシンポジウムを通じて、この企画が広く社会に発信されていくことを期待しています。
あと、美術館を見せていただいたんですけれども、3名の作家の作品が入れ子状、スパイラル状になっているんですね。CSPの示す、「CREATIVE SPIRAL」にふさわしいインスタレーションになっていると思います。
今まで美術館の展示をいろいろ見てきたんですけれども、今回の構成が非常にすばらしくて、この美術館もこんな風に使えば、このような展示ができるのかなと感じてうれしく思っています。今後も、美術学科の卒業者の方々が、芸術表現を継続させ、社会に向けて力強く発信していただきたいと心より願っています。
それでは、高橋先生、藤井先生、よろしくお願いいたします。
- 藤井:
- つづきまして、登壇者をご紹介します。パネリストは、本展の出品者である青木豊さん、荒井伸佳さん、鈴木俊輔さん。いずれも、本学の美術学科で絵画、彫刻を専攻したアーティストです。また、インディペンデント・キュレーターのロジャー・マクドナルドさんにゲストパネリストとしてご登壇いただいています。
そして、本学絵画専攻の教授で、本展のキュレーションを担当した高橋淑人。モデレーターは藤井が務めます。まず、高橋さんからシンポジウムの趣旨についての説明をいただきます。
- 高橋:
- 高橋です。本日はお忙しい中、ありがとうございます。今ご紹介いただきましたように、CSPは今回で4回目を迎えることになりました。昨年は、東京造形大学の50周年記念の展覧会がありまして、CSPという形ではうたっていないのですが、今までの絵画と彫刻の卒業生達を紹介させていただきました。
今回CSP4が初めて、東京造形大学の付属美術館のスペースで展示をするということになりました。いろいろなアプローチの仕方があると思うのですが、昨年の3331のシンポジウムの中で、すごく重要な、考えなければいけないことがあるなと感じました。やはり、美術大学、あるいは美術というものをどう考えるかという部分が、重要な所にきているのではないかと自覚しています。現代、どんどんどんどん表現というものに、いろいろなスタイル、あるいは多様性みたいなものが出てきている。そういう中で、美術大学としての教育としてどういう風に考えるのか。その中から方法論を打ち出すことというのは、一つの価値観を打ち出し、トレーニングすることだけではもう済まない。もちろん、それはとても重要なことではあるのだけれども、それが一番のメインの問題ではないだろうと。もう一度、ある意味で美術というものを考えるときに、原点に戻って考えてみたら面白いのではないかなと思います。それでわざと、3人という少ない人数を選ばせていただいて、全く違うタイプの表現をなさっている作家を選ばせてもらいました。
その中で、美術を考える中でとても重要な、大切だと思うことというのは、それぞれの作家のテーマ、誇り。今回でも、三人一人ずつの仕事を紐解いていきますと、出てくる言葉というのは違うと思うんですね。その言葉もそれぞれとても重要な言葉なのですが、でもそのまた先にある、もっと先にある大切なことというのを常に考えていきながら、時代とか、そういうものも含めて検証していかなければいけないんじゃないかなというところに至りました。
今回は、「あること ないこと」という少しふざけたタイトルになっておりますが、そういうことも含めまして、「あること ないこと」という、そのキーワードを考えます。みなさまにも今展覧会を見ていただいて、いろいろな感想を持っていただいたと思いますが、その部分で何がそれぞれ大切なのか。作家の方の手がかりになるモチーフですとか、制作するプロセス、あるいは掴みたいものというのは、それぞれ、言葉にすると違うと思うのですが、その先にあること、を少し何か考えられる時間になればいいんじゃないかなと思っています。よろしくお願いいたします。
- 藤井:
- 美術の原点として大切なもの、こういう時代だからこそ大切もの、それをどのように考えていくか。そこで今回、キーワードとして「あること ないこと」が出てきたというお話しでした。このお話しに基づいて議論を始めていきますが、まずはロジャーさんに基調講演というかたちで、展覧会を超えたところまでの広い範囲でのお話しを伺いまます。それから出品アーティストのみなさんに、作品について紹介していただくという順番で進めていきます。
- ロジャー:
- 藤井さんありがとうございます。みなさん、こんばんは、ロジャーです。高橋さんから、半年前くらいに今回のお話をいただきました。そのときにお話があったのが、「あること ないこと」を今回のテーマ、タイトルにしたいということ、そして、シンポジウムでなにか話ができないかということでした。そのときに、どういうことを考えているのかというのを高橋さんから伺いました。今日はこのタイトルから私的に響いたことを大枠として少し提供し、皆さんと共有したいと思います。
「あること ないこと」ですが、日本語の日常用語の中で、スラング的なニュアンスがあるそうなんですけれども、私は単純に「what is placed、 what is not placed」と読みました。これを美術的に考えるときに、非常に個人的にやってきた研究と合うと思いました。それは大きく言えば、近代美術史と、spirituality、わかりやすく言えば宗教学を、研究テーマとして博士以前からやってきたので、このテーマは本当にコアな一つの問題意識としてあるものです。要するに、アーティストが物質に対して行う行為と、その物質の裏とか向こう側にある作家の意思とか、時代性とか、あるいは宗教的な考え方とか、人間の体験などです。まさにその辺の問題意識を持って、美術を見てきているので、本日はここからお話をしたいと思います。
いうまでもなくこの関心というものは、美術の長い歴史を見ても、本当に多くの作家が意識を向けてきたことだと思います。これは、どの文化を見てもそうです。あらゆる文化、美術の中でこれが最も現れた方法、あり方というのは、いわゆる「宗教芸術」と我々が呼ぶようなものかもしれません。いわゆる見えない世界を見える世界に移す。Transmissionするという歴史は、長く東洋でも西洋でも、南でも東でもありました。アートは、そういう意味では、まさに知覚の端とか限界、visibleとinvisibleのその領域の間を行ったり来たりしてきた人間の行為の一つでもあるのかなと私はずっと思っています。
今日は議論に何らかの参考になればと思い、3点だけ、歴史的な作品を参照します。
まず、このスライドは、フラ・アンジェリコの15世紀半ばの絵で、「annunciation」というタイトルです。日本語でいうと「受胎告知」ですね。聖書のシーンを描いているフレスコ画です。小さな絵なんですけれども、これは、フィレンツェの修道院の、お坊さんたちが寝泊まりしたcellみたいなところに直接壁に描かれたものです。行ったことある方、いらっしゃいますか? 素晴らしいですね。
この絵を見始めると、一つ、今日のテーマにも響くものが多くあるのかなと思っています。まずは、ここを考えていきたいと思います。このようなヨーロッパで長年続いてきた写実的絵画を見る時に、「読み始めるクセ」、というものがあります。これは特にヨーロッパではそうですね。ルカの受胎告知という聖書のワンシーンを見せているので、目に見えるものを読み始めるんです。例えば、「これは聖書のストーリーだよね」みたいな感じで、絵画なんですけれども、それをイメージ、言語化していく作業が行われていくのです。そういう形で絵が、読めるものとして可視化されてきます。絵が目に入っていくというか、読めるようになる。実はこの作品は眺めていると、非常に不気味な作品でもあると思うんですけれども、読み始めていくと、美術史とか、技術の分析みたいなもの、その物語の中にどんどん飲み込まれていくということがあるのではないかなと思います。でも、さらに長く絵に注意を向けていくとどうなるかというクエスチョンが大事なことだと思います。
次のスライドです。この絵をもうちょっと見ていくと、さらに不思議な絵でもあると思います。あまりディテールがなくて、この時代によくあるような感情表現、あるいは、物語性がほとんどない、とも言われている絵なんですね。絵の中心は、ほとんど白い壁で構成されています。単純、もしかしたらナイーブという言葉を使ってもいいかもしれません。実際、美術史の中ではアンジェリコは、ナイーブなアーティストとも呼ばれてきた方なんですけれど。例えば一つの読みとして、何も描かれていない中心のこの白い壁は、目に見えないものを指している―神の領域だ、と解釈する。このように単純すぎるように読み取る傾向もあります。全てをメタファー化してしまう、全てを例え化してしまう。そういう読みをしちゃうんですね。それは、美術史学者たちには結構よくあるような流れだと思いますが、これはやはり絵画というものから形而上学の領域にただスライドしていくだけの話であって、絵画としてこれを見ていることではなくなってしまう。「It’s a painting image on the wall.」。これが一番大事な現実なんだと思うんです。聖書の何とかとか、テキストとして読む前に、「It’s a painting image.」なんです。
フランスの美学者でジョルジュ・ディディ=ユベルマンという人がいるんですけれど、彼はこう言うのです。「絵画は目に見える知識の伝達だけではない。なにか啓蒙してくれる。情報転換してくれる道具だけではない。絵画は、知識そのものを解体するメディウムであり、解体する道具でもあるはずだ」と。今、絵画はと言いましたけど、もしかしたらこれをアートという言葉に差し替えてもいいかもしれません。あるいは、このディディ=ユベルマンの考え方を推していくと、絵画は「非-知識」の領域にたどり着くかもしれません。「Non Knowledge」、「非-知識」の領域に我々を連れて行ってくれる。絵画を長く、注意深く、コミットメントを持って見る、観察する、鑑賞する行為の中から生まれてくるのは、結論を出せない自分が見えてくるということではないかと思っています。認識し得ない、把握し得ないような領域、いわゆるディディ=ユベルマンのいう、非-知識という領域も実は絵画経験、美術体験の中から出てくるのかなと言えると思います。
「これは、こうだよね、これは聖書のこういうシーンだよね」、という結論に達する瞬間を宙吊り状態にすることの大切さ、結論を簡単に、単純に持っていかないことが、実は作品にはできるのではないかなと思います。
さらには、何かを見る、作品を見るという行為というのは、常に不安定な行為だと思います。特に作家たちは毎日アトリエでそれを確認するのだと思いますけれども、常に変わっていく現象とか、impressionなどを受けていると思うので、そういう中で何かを結論づけていく、何かを読む、言語化していくというその矛盾、難しさというのは常にあると思います。もしかしてこのアンジェリコの絵というのは、一種の交差点のようなのとして考えてもいいかもしれません。無数の意味とか解釈とか、感情とかが交差している。そして、そこから生まれる可能性とか、ポテンシャルですね。我々見る側もそこに想像ができる、想像が泳げるような場所を、アンジェリコは絵の中で作ってくれている。そういう感じもします。
もしかして彼は、目に映らないような何かを、絵画という言語、絵画という文法に落としていっている。これがアンジェリコが出した一つのモデルではないかと思います。
次のスライドをお願いします。想像が泳げる場、ということについてはいろいろな文化の絵画、アートの中にもあって、高橋さんが大好きな中国の北宋の絵画にもあると思います。このスライドは、北宋の荊浩が描いたもので、約1000年前の絵です。中国のこの時代の水墨画、風景画も、想像、鑑賞者の想像が泳げる場を見事に作り上げている作品の一つだと思っています。これは実際の風景を写実的に描いたものではないと私は理解しています。長い間自然観察をし、その自然観察を描く場所に持って帰って、半分記憶、半分は想像、あるいはファンタジーかもしれません。あるいは半分は、遊び、ユーモア…いろいろな要素が描いている間に絵画の中に出てくるので、もすかすると荆浩が具体的に見ているシーンではないかもしれません。荆浩のビジョン。荆浩のビジョンを通ってきた一つの風景がここにあって、これは非常にいつも面白いなと思います。
中国の北宋時代の絵画論の中に「良い絵は、鑑賞者が絵の中に住める」という非常に印象深いフレーズがあります。僕はそれがすごく好きで、「絵の中に住む」ということ。「絵を訪ねる」ではないんですね。つまり、一時的に絵を見て、ツーリストのように少し見て帰るのではなくて、絵の中に住んでしまうという考え方。すごいなあと思います。
次のスライドにいきますが、最後に選んできた次の作品は、近代の画家、ポール・セザンヌですね。セザンヌも、今見た、北宋のペインターと非常に近い態度、近い関心、あるいは方法論で絵画に立ち向かって行ったと思います。ご存知かもしれませんけれども、セザンヌは日常、絵を描く中で、日によって軽く3、4時間、何も書かずにただ風景を眺めるという日も多くあった方です。これは、おそらく瞑想に近い状況、そしてその中で読み取るエネルギーであったり、光の変わり目であったり、何かを絵画を通してセザンヌは常に、追究している。探している、サーチングしているんですね。セザンヌの作品を眺めていると、解決ではなく、永遠に追究している感覚を強く感じます。何かを終わり、解決という方向に持っていこうとはしていないペインターだなといつも思っていて。これはよく宗教学的に例えを取ると、宗教の中では宗教者の方達は何かを常に探る人たちです。しかし、いわゆる宗教の信者たちは何かを信じているので、ある程度のところで止まっている。その違いというのが宗教学にはあるんですけれども、そこが面白いなあと。なんかこう信じ切ってしまっていて、安心しちゃっている人に対して、常に何かを探る人がいる。だいたい神秘宗教の世界では、何かを探り続ける道を選びます。
そのほかにもいろいろあるんですけれど、最近2月にロンドンに行った時に、デイビッド・ホックニーの素晴らしい回顧展を見ることができたんですね。彼の本も改めてよく読んでいるんですけれども、彼はとても興味深いことを言っていて、絵画には常に盲点があると言うんですね。「Blind spots」と英語で言いますけれども、盲点って、面白い表現だなと思いますね。だからこそ、絵画はすごく深くて、時間芸術として成り立っているのだと。いくら絵画とかアートを読もうとしても、解釈を求めようとしても、良い作品にはいつも「漏れ」がある。その漏れが、ホックニーのいう盲点ではないかなと思います。知覚表象を超える何かがある。いわゆるいくら描写力もすごくて「これを描いています」みたいな作品でも、なにかそれ以上のものが、絵画、あるいはアートの中に感じ取ることができる。あるいは、漏れてしまう。心理学的にいうと作り手でさえ、もしかして気づいていない無意識が出てしまっている、という言い方もあります。今回「あること ないこと」について考えた時に、ホックニーのことも思い出しました。ホックニーは、特にこの辺のことを注意深く考えていたように思います。現代では、絵画とかアートとかいう時に、そのペインティングの皮膚、境界を見ているのかなという感じもします。作品全てに境界とか皮膚のようなものがあるとすると、見えないものも当然あると思うんです。その皮膚が覆っているかもしれない。あるいは、絵画がそこで表せないものを指している。いろいろなやり方があるような気がします。
これに関して、もう一人、美術学者のノーマン・ブライソンという方がいます。彼は1983年に「目に見えない肉体」というエッセイを書いています。「invisible body」というタイトルなんですけど、まさにこういう問題を絵画に関して理論化しています。
西洋絵画の歴史を見ますと、肉体の表象はたくさんありますよね。肉体を表すというのは西洋絵画の主題の一つで、大きなポイントだと思うんですけれども、画家たちはまさに「読める肉体」として描いてきたのだと思います。いわゆる写実的に描くということですね。「これは裸体ですよ」「これはイエス・キリストの姿ですよ」と、理解しやすい形で描いてきた。しかし、ブライソンは非常に面白いことを言っています。さっきのホックニーの「漏れ」、つまり何かが必ず漏れるということと近いんですけれども、「もう一つの肉体は必ず絵の中にある」と言うんですね。もう一つの肉体とは、作家が意識的に描く肉体と同時に、描いた肉体そのものののことです。つまり、作家の肉体です。例えばティツィアーノのヴィーナスなどを思い出すとわかりやすいですが、西洋の描き方はすごく特殊で、なるべく描いた作家の肉体感覚を消すように、発展してきたのではないかというのがブライソンの指摘です。
確かに、レオナルドの…レオナルドのかどうかもちょっとクエスチョンマークのイエス・キリストを描いた作品がありますけれども、レオナルドの筆致やクセはほとんど残っていないんです。レオナルドの筋肉の動きとか手の動きがほとんど残っていないんですね。それは、そのように描いているからです。これはブライソン曰く、西洋ではもう一つの肉体をなるべく隠すのがペインティングの伝統であったということなんです。
しかし、よくよく見ると、ホックニーのいうような「漏れ」―もう一つの肉体が必ずどこかでバレてしまうというようなところがあるんですね。ブライソンのすごいところは、それを中国美術に転換していくんです。まさに北宋などのことにも言及しているのですが、中国では西洋と異なって、描く人の肉体も最終的に隠さずに見えるように残していて、そこが大きな違いではないか、と。今、この話題の詳細には入っていきませんが、こういうことを「目に見えない肉体」として論じているのです。
今日話していることは、少し難しいこともあるんですけれども、非常に大事だと思っています。我々鑑賞者は「全てを見ることはできない」という理解の上で、作品にアプローチする。そのことがすごく大事なのかなと思います。特に今の時代、私もキュレーターと名乗っていますけれども、現代のキュレーターの多くは、全てを透明にする、全てを言語化する、全てを読めるように落としていく傾向が非常に強くなっています。私はそれはあまり良いことではないと思っています。啓蒙、教育というものも大事でありながら、最終的には、作品そのものにまず向き合わないと、作家に対してよくないのかなと思っています。今日紹介してきた、見ることの中で生まれてくる宙吊り状態とか、全てが実は見えていない、という理解の上で、アート観賞をすると言うことです。あるいは作家達も、もっとこういう意識を持つとひょっとしたら何かが変わるかもしれない。その辺は三人にも聞いていきたいところですけれども、そんな風に思います。この辺で終わります。ありがとうございました。
- 藤井:
- 非常に興味深いお話でした。時代や地域の異なる3点の作品が登場し、それ以外にも、ホックニーやレオナルドも登場して、美術史の広い範囲の中での「見えること」「見えないこと」が論じられました。私にとって、特に興味深かったのは、境界や皮膚という言葉ですね。つまり、「見えること」と「見えないこと」が両義的なものであるということです。「見えていること」「見えていないこと」の両方が常にあり、両者は常に深いレベルで関与している。例えば、ルネサンスの宗教絵画はメッセージを伝えることを目的としていますが、それで終わってしまうものではなく、そこに絵画性があることが重要なわけですね。
北宋絵画の話では、鑑賞者の「想像が泳げる場」という言い方も非常に興味深いものでした。いわゆる「臥遊」と呼ばれる、鑑賞者の意識が画面の中に入って行くものです。さらには、セザンヌの事例。終わりのない追求のプロセスそのものが絵画だということ。それが「見えること 見えないもの」に重要な関わりがあるということですね。
そして、現代の問題についてですが、人間は全て見ることはできないことを忘れてしまう。見ることができるという風に考えてしまう。その点を再検討することから、私たちの日常的な意識を、芸術を通じて問い直すことができるのではないかといったお話だったと思います。
続きまして、出品作家の方から、自作についてお話しいただきます。
- 青木:
- 青木と申します。よろしくお願いします。今日は3枚画像を提出させていただいてまして、これを手がかりに、これまでの制作を振り返ってお話させていただいて、本展で、どういったところにアプローチできているのかというお話をさせていただければと思います。今出していただいているのは、今年の作品なんですけれども、2009年くらいからこうしたシルバーの作品を作っています。シルバーの作品を制作しているときにメインとなっているモチーフは、山脈であったり山であったり、そういったものを描いています。ロジャーさんの話も「そうだな」と思って、聞いていたんですけれども、先に制作の方法をかいつまんでお話させていただくと、まずは下地を作り込む段階で、まっさらなキャンバスの面を消すような形で、何層も何層も下地剤を入れて、ヤスリがけをしながら、まっさらなフラットな白い画面を作ります。そのあとに同じ白い色材を用いて、山を描いていきます。なので、自分の中で何を描いているか、この時点ではわからないんです。どうなっているのかというのは、まず真っ白い画面が出てきて、自分でも理解できないという状態を一旦作り上げます。その時のプロセスとしては、絵の具の盛り上がりであったり、陰影が落ちて、その陰影を手掛かりに、「ああ、こうなってるんじゃないかな」と想像しながら作っている感じです。そのあとマスキングをして、シルバーのクロムメッキと言いますか、光を反射するような塗料を持って、スプレーで吹き付けて仕上げるんですけれども、今ロジャーさんがおっしゃったように、自分が作るといった時に、常に自分が作品を作っているというよりも、「作品はもうある」という感覚なんですね。言葉がちょっと抽象的すぎるんですけれども、ずっとどう言葉にすればいいんだろうなというのがわからなくて、7、8年、悶々と制作をしながらきたんですけれど、ここ2、3年、ようやくちょっとずつわかってきたなということがあって。「こういうことかもしれない」と。言葉としては、今、個人的にキーワードになっているのは、アフォーダンスという言葉。ジェームス・J・ギブソンという心理学者の方が提唱されたそうなんですけれど、適正な言葉で今ここでお話できるかどうかわからないのですが、内容としては、環境自体が動物に与える意味性、みたいなことなんですね。
環境が動物に与える意味。これを自分の中で考える時、意味という部分を、環境が動物に与える問いかけ、というように僕は解釈しています。これは、日本の佐々木正人さんという人が本を書いていまして、佐々木さんは、「表現の肌理」という言葉で表現されているんですね。まさにそうだなという。自分の中で腑に落ちたというか、自分がやりたかったというか、求めていたのはこういうことなのかもしれないなと。自分なりに最近、作ってきたものと、自分と作品の立場と、その環境ですね。そういったものが少し整理できたかなと思っています。
スライドの二枚目をお願いします。こちらは、先ほどのクロムメッキの画面で一度仕上げて、左の側面から、レモンイエローのスプレーをクロムメッキの上に吹き付けて、右手からは、パステルブルーを吹き付けているんですけれども、そうすることによって、自分が作品のどの位置に立つかで色味が変わっていったり、本来であれば、隆起している絵の具の影が落ちているのがむしろ発光して見えたり、絵画上のイリュージョンと言いますか、そういうのとは別のアプローチで、空間であったり、絵画というものを、考えることができるんじゃないかと思っています。視覚的な効果というと言葉が軽すぎますけれども、絵画を問うための仕掛けとして、色彩が持つ力といったものを、作品に入れて展開しています。
三枚目をお願いします。これは、雰囲気がガラッと違うんですけれども、先ほどの、環境が動物に与える問いがアフォーダンスだったとすれば、今度は、動物が環境にどういった問いというか、問いかけ、相談、という言葉かどうかはちょっとわからないんですけれども、そういったことができるのかなということで、ここ2、3年、このシリーズも展開しています。
これは、和紙、正確には和紙ではないのかもしれないのですが、内装をする際の障子紙と言われるものですね。壁に紙を張り込んで、壁を立ち上げる時に障子紙と言われる和紙の一種の紙があるんですけれども、それを張り込みまして、カッターで水平状に薄く、紙の薄皮一枚線を入れて、それを剥がすという形で作っています。基本的に、同じように、同じ角度、同じ力で剥いでいくんですけれども、実際には、剥がれ方はそれぞれ違うという形でできてきています。どうやってまとめていけばいいのかわからないのですが、そういった感じで、絵画を考えるときに、環境と、自分が動物であるということ、そして、シルバーのシリーズで展開してきた、ロジャーさんも先ほどおっしゃっていたように、どうやったら見えないものに対して、自分がきっかけをつかめるかという形で、骨格じゃないですけれど、そういう感覚で制作を今、進めています。
- 藤井:
- 今回のテーマに関連して、私が青木さんの作品で興味深いと思う点は、絵画のイリュージョンの問題についてです。例えば、白色とシルバーの関係性では、どちらが手前でどちらが奥か、見ているうちにだんだんと混乱してく。それは、実は、白色と銀色の関係そのものだけではなくて、白色部分のエッジが非常に丁寧に作ってあることが重要な役割を果たしています。そのことによって両者の関係性が切り替わる。もちろん、色であったり質感であったりの違いが重要なのですが、それだけではなく、違う部分も大きく影響しています。
- 荒井:
- 荒井伸佳と言います。よろしくお願いします。僕は、作品を作るときの基本のスタンスからお話していきたいと思います。まず、文化の成立の仕方であるとか、歴史であるとか、人類のスタンスというか、そういうことに興味があります。常に人間と社会のあり方みたいなものを念頭に置いて彫刻作品を作っています。また技法や素材はその時々で変え、素材に関しましては、基本的には比較的身近に手に入りやすいものを使って構成するようにしています。
今回、「あること ないこと」というのがテーマで、ちょうど僕自身も人間の存在というか、そういったものをすごく気にしていて、彫刻自体が物質として存在するということが根底にあるのではないかと意識していますので、その辺の問題もテーマとして扱っています。
この作品は、<Nowhere Now here>というタイトルになっていて、少し言葉遊びのような要素を含んでいるんですけれども、Nowhere、「どこにもない場所」みたいなことなんですが、形は看板をモチーフとしています。看板というのは、どちらかというと存在をアピールするようなものだと思うんですね。ただ、これはセンテンスの切り方によっては、Now here。「今ここにいます」という感じの作品になります。ちょっと不思議な感じというか、逆説的な言葉遊びのような感じですね。
次お願いします。こちらは<集合と自立>というタイトルの作品になっていまして、まさにタイトル通り、いろんな木の破片で構成されていて、それらを結束バンドで縛り固定することによって、自立しているという作品です。集合であったり個であったり、個の集合体が結束して自立するような形を意識しています。彫刻というのは、重力に非常に左右されますので、自身で立つというのが、一つの彫刻の問題だと思って、それを意識して作品になっています。
今回は、この2点以外にも他3点作品を出品しています。あまり平面の作品を作らないのですが、前回のグループ展で、「下品」というのをテーマにしていまして、普段あまり「下品」ということを意識することはなかったんですけれども。話を圧縮して話しますけれども、下品というのは、何か新しいものを生み出す行為自体のことではないかというスタンスで、作品を作りました。今回の作品とも絡んでおりまして、その平面の作品は、マルセル・デュシャンに対するオマージュとして作りました。デュシャンほど下品な作家はいないのではないか。新しいことというのは、やはり常に大きな文脈の中で異質なことをする、というのかな。上品なことというのは、価値の定まったものと言いますか、価値が定まっているということは、既に伝統文化として確立していたり、ある程度時間が経っていて、評価が定まったものを指すことが多いと思うんですね。歌舞伎も出始めは、決して上品なものではなかったと思うけれども、数百年経つと上品なものとして解釈されることは文化の中でよく起こりうるのかなと思っています。デュシャンは、まさに現代美術の先駆けと言われるようなビジュアル的に上品でない作品を作っているということを踏まえた上で、そのオマージュ作品を作りました。
また今回、神話をテーマにした作品を作ったのですが、最初、マンズー先生の作品が常設で存在していて、これをどうするか、という話が打ち合わせの時にありまして、これを隠す方法もありますよということだったんですね。衝立を立てることによってそれを隠してしまう。それこそ「あること ないこと」という話になってくるんでしょうけれど、僕自身は、隠すぐらいだったら一緒にコラボレーションできたらいいなと思って、今回のああいう作品にしました。結果的に覆うことによって、逆に強調するという意味もあるのかなと思ったりして。また、ものを生み出すことをする人たち、よくクリエイター(創造主)と言う言葉がありますけれども、今回のマンズーの作品は、「恋人たち」というタイトルが付いていまして、彼らはまさにモチーフとして何か作ろうとしている行為から付いたのかなと言う風に考えて。これはちょっと変な見方ですけれど、彼らはずっと創立当初から、晒されている状態ですので、たまには、囲ってあげて、二人仲睦まじくそっとして置いてあげるような、そういうアプローチをしても面白いのではないかな。ということで、作品として成立させました。
- 藤井:
- 新井さんの作品で興味深いのはシンタクス、繋がり方の問題ですね。例えば、人体であれば胴体、頭部、手足などに不変的な繋がり方がありますし、抽象彫刻であっても、部分と部分の関係性には一定の約束事があります。でも、荒井さんの作品ではそうした約束事が破壊されている。脚立のうえにフクロウが置かれたり……普通ならここでこうは繋がらないでしょ、みたいな。(笑)ロジャーさんの指摘された「知識そのものを解体する」ような作用があるのかもしれません。
- 鈴木:
- 鈴木俊輔と申します。よろしくお願いします。最初の作品ですけれども。いきなり汚い写真なんですが、これは僕が大学4年生の頃、東京造形大学で製作している風景になります。僕はステートメントの最初にいつも書いてあるんですけれども、何も考えずに、ただぐちゃぐちゃに塗りつけられたキャンバスの中に、一点の美しさを発見すること。とありますけれども、とにかく、自分は何も考えずに体でキャンバスに向き合って、何かを引き出してくるという描き方をひたすら、学生の頃は求めて描いていました。その頃は、自己と絵画の一体化というように考えていまして、自分そのものがキャンバスに張り付いたように、なにかこう、全てが絵画と一体化して、イコールになるようなことを、バカみたいに求めてやっていました。なので、知識として絵画を考えて描いていくということはなくて、自分がキャンバスの前に立っている時間だったり、描く量だったりというものを、作家として描く自分の大切なものとして、制作を続けていました。
次のスライドをお願いします。これが2010年、10年後の作品になります。同じような感じで、何もイメージを持たないで絵の具を塗り続けながら描き続けていくというのをやっていきました。その中でも、ひたすらそうやって描いていく中で、少しずつ自分の絵というものが変化していくようになります。色も、出てくる形というのが少しずつ変化していきます。その変化というのが自分が日々、生活していく中で、この時は子供の絵画教室を始めるようになって、子供に絵の楽しさだったり面白さだったりを伝えるということを仕事にしていく中で、今までは自分そのものがキャンバスに張り付いていくというように考えていたものが、ちょっとずつどのように絵画というものが伝えられるかみたいなことを考えるようになってきて、ようやく形が変わってきました。やっぱり子供に教えたり、障害がある人たちにも教える機会があって、という仕事をしていたんですけれども、子供たちが引く線だったり、使う色、その時のエネルギーだったり、というものが自分の中に影響を与えて、キャンバスの中に自分が向かう時の変化、意図的に子供の何々を取り入れようとかいうつもりはないんですけれども、自然と描き方の中で変化していくという形で、制作をしていました。
次のスライドをお願いします。これは、今回も出品している顔の作品です。2、3年くらい前から、ただ何も考えないでぐちゃぐちゃ塗りつけた中から絵を引き出してくるという描き方ではなく、ある程度具体的なイメージを持ちながら、制作するという風に変わってきました。それというのは、僕の中で今までの描き方というのは、イメージを描くこと自体、否定をしていたし、何か線を引くということ自体が信じられないので、体で線を作りながら描いていくような感じでできたものが自分の中で真実の線だと思っていたんです。でも、最終的にそのようなやり方で出てきたもの、色や形、画面の構成というものが、ようやっと最近、その上澄みというか、最終的に出てきたイメージを最初から定着させるようなやり方にだんだんと描けるようになってきたのかなあという風に思っています。じゃあ、最終的に出てきたイメージとはなんなんだということになると思うのですが、これはちょっと唐突なんですけど、例えばこの顔の作品というのは、水俣病の胎児性の患者さんの写真からイメージをとって描いたものです。今回の作品は、そのような写真のイメージを使って取り組んでいる作品が何点かあリます。ちょっとうまくその辺りは説明できないんですけれども、僕の中で大学生の頃に描いていた、「格闘しながらも、求めている1点の美しさ」という風に、ステートメントで書いていますけれども、そのことと、水俣病の患者さんが、ひどい被害にあいながらもそれでも生きていく姿を捉えた写真だったり、そういったものと、僕の中ですごく一致するものがあって、今までは写真を使って表現するということはできなかったんですけれども、今回はそういったものを自分の中で消化して、何かの形と絵画にするということができ始めてきたのかなという風に感じて、今回、作品を制作してきました。以上です。
- 藤井:
- 今回の展覧会の出品者の中では、鈴木さんがもっとも具体的なイメージをもった作品を出品しています。とはいえ、それが前提になっているわけではない。実際には、そこに到達するまでに様々なプロセスがあるという部分が興味深かったです。それは、結果や結論を前提としたものではなく、自分が生きていく中で到達した「あること ないこと」とも呼べるのでしょう。
次に、今回の展覧会の会場構成についてお聞きしたいと思います。これは本展のキュレーションを担当した高橋さんが設定されたわけですが、会場に関していえば、付属美術館はとてもクセの強い場所といえますね。さらに、入口から見て右側の部屋、主に青木さんの作品がある部屋を暗くしたことも特徴的です。こうした条件の中で自分の作品をどう考えたのかを聞きたいと思います。
- 鈴木:
- 今回の展示に関しては、今、最後に話した部分というのはすごくあるんですけれども、布の作品が、すごく僕の中では挑戦というか、初めての試みでした。今までは、絵画というものの中で、ずっと取り組みをしてきたんですけれども、今回、マンズー美術館の特殊な構造というか、面白い構造の中で、自分のやり方を活かしながらどのような作品が作れるかなということを考えた時に、キャンバスという支持体を超えて、空間を作っていけるようなものということで布の作品を制作したこと。それは僕にとって大きなチャレンジだったし、収穫でもあったなあという風に思っています。
- 藤井:
- 木枠に貼られたキャンバスのように明確な矩形があれば、そこで区切って考えることができますが、それは会場とは分離した状態とも言えますね。逆に、木枠に張らないキャンバス地を天井から垂らした場合は、作品と空間が一体化していきます。さらに、絵の具が表面に乗っているのではなく染み込むようになっていて、描かれているイメージが空間と一体化する方向性を示している。この作品の存在が今回の鈴木さんの展示の中で独特の空間性を生み出していたと思います。
- 荒井:
- 今回、結構広い空間の中での三人展ということで、いろいろな意味で考えさせていただいて、青木さんと鈴木さんの作品は絵画で、立体は私だけだった。そんな中で、どういう風に展開しようかなと思って。
最初の打ち合わせの中で、美術館の左右の空間を対峙させたら面白いのではないかという話が出たと思います。左側と右側の空間とがあって、入って右側の空間は、暗くして、どちらかというと、陰と陽みたいなイメージ。あれだけ暗い空間の中で作品を展開するというのは、あまりないことなので、実験的で自分の中でも普段しないような、面白いことができたらいいなと思いながら作りました。
- 藤井:
- 荒井さんの作品は明るい部屋と暗い部屋と両方に展示されていますが、そこで、作品を変化させるか、同じようにやるか、その点をどう考えましたか。
- 荒井:
- そうですね。
- 藤井:
- そこで、作品を変えようとか、同じようにやろうとか、そのあたりどうお考えでしたか?
- 荒井:
- ちょっと変えていこうかなと思いました。最近、作品自体に、それこそ見えたり見えなかったり。「あること ないこと」というのにちょうど合致するんですけれども、作ったものに薄い布みたいなものをかけたりとすることが多かったのですが、鈴木さんの作品も布という話を聞いていたので、明るい方の空間ではでは布をメインにしない形でやってみようと思いました。
- 藤井:
- 青木さん、お願いします。
- 青木:
- 僕は学生の頃から、マンズー美術館で展示をしたことがなかったんですね。マンズー美術館は、学生の頃は、白い壁ではないというだけで、なんとなく敬遠していたんですけれど、今回の打ち合わせの時に久しぶりに入ってみると、すごい空間だなと改めて思いました。胎内の中に入ってきちゃったかなみたいな感覚になったんです。ダリの言葉じゃないけれど、毛深さを感じるというか。そうした時に、「あること ないこと」という展覧会のキーワードと、あの建築の空間と。これはちょっとすごいなと思ってですね。両側にスリットが入っていて、自然光も入るということと、あれだけの雰囲気を持っているんで、片方の照明を落とすというプランが出た時に、これは、なんというのかな。精神性のところも、すごく出せる展覧会になるなと思いました。それで、天井から照明を落とすのではなく、床から照明が当たっていて、下の方に光が落ちて陰が落ちるのではなく、下から発光して広がっていく中で、暗い空間に何かが立ち上がっていくような。すごくチャレンジさせていただける場所とテーマだなと思って、高橋先生が「チャレンジ、いいぞ」と背中を押してくれたので、これは三人それぞれの作風がある中で、すごく対比的な、一周回って、あの建物の外に出た時に、何かを持ち帰れる展覧会にできるんじゃないかと。それでああいった構成になっていたんだと思います。
- 藤井:
- 続いて、今回の展覧会の感想をロジャーさんと高橋さんにお聞きします。
- ロジャー:
- まず、マンズー美術館の建物ですね。比較的私は好きな建築空間なんですけれども。チャペルっぽいというか、いわゆるサロン風な要素もありながら、温かい雰囲気ですね。コルビュジエ的なカチッとした感じではないです。これが今回のテーマに、すごく合うような要素もあるのかなと思いました。暗い部屋の壁の上に付いてる、十字架っぽいもの、あれはライトですか? 修道院的な要素もあって、部屋自体はすごく暗い中で見るという。そういうチャレンジングな環境の中で、paintingを見せるという素晴らしい展覧会だなと思います。
キュレーションの歴史の中で思い起こされるのは、34年くらい前、シュールレアリストが真っ暗闇の中で展覧会をしたことです。キュレーターはマルセル・デュシャンですね。全部ライトを消して、お客さんに懐中電灯を渡して鑑賞するという展覧会です。すごく上手だなと思うのは、懐中電灯で照らされたところがまさに自分の意識のあるところであとは闇。これによって無意識と意識という精神の世界を示すという、すごいメタファーとしても美しい展覧会なのです。実際に見てみたかったですね。そういった闇の中の展覧会というのはすごくありそうで、特に近代ではあまりないなあと思います。高橋先生も、できれば思い切りやりたかったんですよね。もちろん美術館のルールはあると思うのですが。まさに陰と陽、明るさと暗さという要素があったりして、どこかにそういった普遍性のある要素が感じ取れる展覧会だと思いました。
- 高橋:
- 全部僕の勘で考えていたりするので(笑)。ただ、最初テーマを考えまして、三人の作家の方を選んでいく中で、どうせだったら普段、例えば、すごく大きなスペースでなければチャレンジできないとか、ということはすごく考えます。あと、全くタイプの違う3人の作家たちの中で、グループ展の中ですごく重要なことというのは、それぞれ違う出品作家が、それぞれ違う答えを見つけているんだけれども、何か大きな感覚が立ち上がってくる。一つの言葉で言い切れないけれども、そこがやはりすごく大切なんじゃないかなと思います。そういう意味では、思い切ってライトを暗くするということ。正直、最初から僕の方から作家さんを煽っていたんですけれど、実際に展示してみると本当に真っ暗で、特に、絵画は見えないよと。でも反対に、その時覚悟を決めたんですね。その、見えないというところを徹底的にやった時に、かえって見ようとする、例えば山の中で夜、木を見つめていたとします。最初は、真っ暗で見えない。だけど、だんだん時間が経つ中で、そのシルエットを感じて見えるようになってきて、もっと目には見えないものでも察知しようとする感性みたいなものが働き出すんだと思うんです。今の時代というのは、あまりに明るさに慣れていて、固定化された情報に頼りすぎていて、自分たちが、今自分がいることを理解するために見ようとする、あるいは感じようとするみたいなことは、欠落していっているんではないか。そういうことも少し提案できればいいんじゃないかなということを、後になってその理由を考えました(笑)。感覚的に「これだよ」って思ったというのが正直なところです。
- 藤井:
- ここまでのお話しを受けて、さらに、ふたつのことについて議論していきたいと思います。第一に、ロジャーさんのお話しもありましたが、展覧会の企画者はどの程度それをコントロールするべきなのか、ということです。これは、展覧会テーマの「あること ないこと」にも結びつく問題だと思います。さらには、人間というものが本来的に有限的な存在であるということにまで関わる問題です。
第二に、今回の展覧会における、現代の社会との影響関係などについて。絵画や彫刻は形式的に経験することもできるものですが、一方で、アーティストは生身の人間として社会の中に生きている。当然、社会にも影響を受けながら、ものを考えるわけです。それは、特に、今回のコンセプトの文章にある「異常な速度で逆走し、暴走しだしたこの時代だからこそ大切なもの」という部分に関わります。美術は社会の中で完全に独立してあるのではない。その繋がり方という問題に触れていきたいと思います。
まずは、直接的に作品にはならないかもしれないけれども、アーティストとして今の社会を生きていて、感じること、考えること。それと芸術との関わりについて。
- 青木:
- 今回の展覧会のステイトメントにもあるように、どうしたって薄っぺらいというか、社会自体が薄っぺらさを持っていると思うんですね。アートの中であえてそういう身振りをやっている作家も多くいると思うんですね。ウェイド・ガイトンという作家は、そういったところの身振りをうまく使って逆説的なアプローチで本質を見ようとしているのかなあと思うんですけど。薄っぺらさを手掛かりに本質の方に螺旋状に入っていこうとしている、そういう作家は多いと思うんですけれど、その薄っぺらさを操縦しすぎると、実は螺旋になっていなくて、同じところをぐるぐる回って、問題がどんどん横滑りしていっている印象も個人的にあります。そうした中で、ささくれみたいな、そこの切り口をどう掴んで、内側にぐいっと入っていくか。それがすごく難しいんだと思うんですけれど、社会がそうであるとして、美術がそこにどう寄り添えるかという時、そのささくれみたいなものを出すというか。それを表出させうるものが美術なのかなと思います。
- 藤井:
- 自分の活動が社会に受け入れられたいというのは当たり前なのでですが、その時に、美術の方から社会に合わせていくのかという問題があります。社会の「薄っぺらさ」と言われましたが、それを批判しながらも、同時に、アーティストはその中で考えながら作品を作っていくより他はない。そのことも両義的な「あること ないこと」と言えるかもしれません。
- 荒井:
- 色々と考えることはたくさんあるのではないかと思っていて、まさに、先ほども申し上げた通り、そんなことを考えながら作品を作っています。今、色々な意味で社会の転換期だったりするのかと思ったりしております。今の社会構造って、狩猟から農耕に移った時にできた社会構造がもとになっていると思っています。基本的にはその構造は変わっていなくて、それが今の世界的規模での格差社会につながり、トマスピケティが「21世紀の資本」を書いたりして、大きな問題になってきているのかと思ったりもしております。また人口が、爆発的に増えていると言ってもいいんでしょうね。先進国では減っているのですが、人類としては今までにない規模で増えている。そういう局面に入っているのかなと。人類はこれからどういう方向に向かうのか。最近、スティーブンホーキング博士の未来予測で、これまで人類の最後は1000年後と言われていましたが、意外に早く100年後には居なくなってしまうかもしれないというような話も出てきたりして、色々考えるべきことがあるなと思ってしまいます。僕ら美術家は、そんな社会状況を感じながら、芸術家としての表現をしていく必要があると思っております。そして美術家は、いろいろな制度から自由であるべきなのかなと思っています。自由の定義っていろいろあると思いますが、例えば、今の資本主義の社会構造に、絡め取られないようなスタンスで作品を作れたら面白いのかなと思っています。ただ、現社会に生きて入る以上、もちろんそこに埋没して、社会生活を送らなければいけないのですけれども、美術家としてのスタンスというか、作品のあり方は、そこから自由なくてはならないと感じております。
- 藤井:
- 自由であるということは、自分勝手であるという意味に受け取ってしまいがちですが、実はそうではない。むしろ、こうした社会の中では、アーティストは自由であるという義務を持つと言った方がいいかもしれません。
鈴木さんは先ほど、子供の絵画教室で直接的に他者と向き合う中で作品が変わってきたという話をされました。その延長になると思いますが、社会人として社会の中で作品を作っていることについて。
- 鈴木:
- 青木さんが言っているのと同じかもしれないですけれど、僕なりに社会とのつながりということを考える時に、僕は個人であるということとか、つながりっていうことをつなげて何かにするという、そのことを否定するわけではないんですけれど。とことん個人として、何かを見つけていくというところが、作家にとってということなのかもしれないし、人は誰でもそうなのかもしれないですけれど、個人の見方だったり、というものをどれだけ掘り下げてそれを表出して表現していくということで、社会と関わって行くということが、僕は作家として大事だと思っています。ロジャーさんの話の中で、皮膚というものの向こうに見えないものがたくさんあるとおっしゃっていましたけれども、まさにそれをどう見つけていくか、見ていくかということを、探っていくこと。それが現れた時に、またそれを見てくれた人に、何か解放するような、作用を持って社会に還元されていくものとしての作品の役割というのがあってほしいなというのはあります。
- ロジャー:
- すごく大事なポイントを2つ指摘したいなと思います。「アートと社会」って、日本では3.11以後多く話されてきているテーマですが、作品に注目しすぎている傾向があるのかなと思います。どういうことかというと、アート界がアーティスト、または作品に答えを求めすぎていることが気になるんです。これは海外も含めてです。例えば、「関係性の美学」とか、いろいろな形でこれが展開されてきたと思うんですけれど、意外に作品にできることって、戦術的なレベルだと思うんです。小さなサジェスチョンとか小さなヒントとか、一時的な共同体のあり方とか、戦術レベルでは素晴らしい提案がアートにはできると思うんです。では戦略的なレベルではアートは何かできるのでしょうか。もしこの方向性を真剣に考えるのであれば。戦略的なレベルで動かなくてはいけないのは、アートの制度なのです。例えば美術館、キュレーターとかがもっと声をあげるとかしないといけない。作家に全てを任せすぎていると、戦術のレベルで満足してしまうんです。僕は「こういう展覧会をキュレーションしました。私の一年分の社会貢献ができたからもうリラックスする」みたいなのが嫌なんです。それだと自己満足的な要素があるなと思います。次の大事な議論は、戦略的に、どうやってアートという業界に何ができるかを考えることだと思います。例えばもう少し具体的にいうと、日本の美術館が共同宣言をしたら、社会的な影響力の持つ良いことができると思うんです。これは…別に何を言ってもいいんですよ。例えばもっと障害者たちにアクセシブルな美術館にするという宣言文書を日本全国の美術館が出しすとしましょう。予算はないかもしれないけれど、「我々はこういう美術館を目指すんだ」って主張することで、もしかしたら、いろいろな人が「そうだね」と言って、予算が出始めるかもしれない。
そういう意味で、作品、作家の次のレベルの議論もそろそろやるべきなのかなと。その議論の場には、もちろん作家もいるんだけど、美術館の館長とか行政の人たちも巻き込んで、戦略レベルでやっていくべきことではないかと、思っています。
もう一つは、鈴木さんのワークショップもその表れだと思うんですけれども、「政治」って、あるいは「社会とアート」の問題って、社会問題を取り上げることだけではなくって、実は一人ひとりの主体性の問題だと常に思っています。その主体性がどう再生されるかとか、主体性から生まれてくるコミュニティだとか、個からつながっていくことによって、また違う実践のコミュニティができるかもしれない。個人的には、60年代とか70年代の実践とかも見るのが好きなので、そういうところからも学べるものはまだまだいっぱいあるなあと思います。アートと社会の中では主体も再生もすごくコアな要素としてあるはずだなと思っていて、そのあたりのことはいつも考えています。
- 藤井:
- 1点目の、アーティストに全てを任すのはおかしい、みんなで力を合わせていこうというのはその通りだろうと思います。2点目は主体性の問題ですね。リレーショナル・アートという言葉などが使われていますが……。もちろん、私も人間と人間は繋がった方がよいと思いますよ。思いますが……繋がりますよという前提の中では、それが可能であるという条件を最初から与えられた中では、逆にコミュニケーションを制限されていくような気がします。
現実には、人間と人間が向き合った場合、相手が何を考えているのかは分からないわけです。その分からない中で、相手に何を伝えられるのか、相手のことを理解できるのかを考えるのがコミュニケーションでしょう。「関係性の美学」とは、本当はそうした場所にあるものです。一人ひとりの主体性がどう繋がることができるのか、できないのか、そうしたドキドキ感の中で向き合っていくというところに意味や価値がある。そうした部分は経済効率からは遠いところにあるために、排除されていく傾向にあります。だから、最初から繋がれることを前提にして、そこでやりましょうという風になっていく。「あるものはある、ないものはない」になってしまっていく。本当は、人間は「ある」と「ない」の両義性の中で生きているはずですが、その部分が欠落していく。今回の展覧会テーマを設定する上で高橋さんが考えられたのも、おそらくは、そうしたことではないでしょうか。
- 高橋:
- この言葉を選んだ時、とにかく本当にあらゆるところで使える言葉だよなってすごく考えました。ただ、すごく重要な部分と言うのは、やはりいろいろな角度で真摯に検証し続けることが一番大事なんじゃないかな。今のロジャーさんの話を聞いていて「ああそうだよね」と思って、じゃあ、アーティストは安心していていいのか、それはキュレーターやギャラリストに任せていいのかみたいなことではないんだと思うんです。お互いがどういう関係性を持っていられるかということに対して、模索するということも大事でしょうし、自分の価値観を備えて押し付けるということではなくて、基本的には自分が存在しているということと、相手が存在しているということが、関係付けられて、初めてそういうものが成り立ってくるということが、僕は一番重要なことだといつも思っています。それは、美術自体もそうですし、人間が存在しているということもそう。それこそ、今の社会のすごく多様性を求める、それを認めながらも一方では、全てを排除していったりとか、否定するみたいな時代の流れみたいなのは、特に最近政治的なレベルですごく気になリます。そういうことも含めて、やはりもっと広い価値観の中で、確かめ合う、あるいは繋がっていくということと自分の力だけではなくて、他のものとの関係の中で、不可能なことを可能にしていくというのが、まさに人間の知恵みたいなことじゃないかなと思います。
- 藤井:
- 展覧会のために書かれた高橋さんの文章を最初に読んだ時に、貨幣のことを考えたんですね。かつての金貨のように金属としての実態があれば、その価値はとても分かりやすいですね。それが近代になると、紙幣に、紙になっちゃうわけです。それも兌換紙幣から不換紙幣になって、金との交換も約束されなくなる。ニクソン・ショックが1971年ですから、それが最終的に確立したのは既に40年以上も前のことです。現在では、そのような話ですらなくってしまって、ほとんど実体のないデジタルの数字になっています。この場合、お金はあると言うのか、ないと言うのか……。お金と社会の関係や、お金を媒介としたコミュニケーションそのものは変わっていないとも言えるのですが、いつの間にか、お金ってあるのかないのかよく分からなくなっている。今、立ち止まってこうした問題を考える必要があると思います。
これは芸術であろうがなかろうが考える必要があるわけです。ただ、私たちは美術に関わっていて、美術のことを考えながら生きていますから、美術を通じてそれを考えることになるはずです。それがこの展覧会の大事なメッセージなのだろうと思います。
最後に、パネリストの皆さんに「あること ないこと」について自由にお話しいただきます。展覧会を通じて、あるいはこのシンポジウムを通じて考えたことなどを自由にお話しください。
- 鈴木:
- 自分の作品のことしか喋れないんですけれど、今回展覧会の話をいただいて、作品ができるまで本当に苦しかったです。何が苦しかったかというと、大きな会場を埋めなくちゃいけないというプレッシャーもあったんですけれども、自分の中で、ちょっと今までとは違う取り組みというのをやらせてもらって、それがどのような評価を受けるかみたいなところ。すごく自分の中でもいいはずだけど、よくないかもしれない。本当に「あること ないこと」みたいな状態でずーっといて、何も確信が持てないまま、会場に来て、展示をして、「ああ、もしかしたら、何かあるかもしれない」というような感じ方を今回の展覧会でさせてもらいました。「あること ないこと」自分の作品の中に、さっきのロジャーさんの話に戻りますけど、見えてないものが非常に多くあるなというのは、自分の中ですごくあるんですけれど、でも、その中に自分が見えていないよさ、と言っていいのかどうかわからないんですけれど、作品の持っている力というようなものがあって、それは、本人は描いているときは気づいていないし、展示してもまだぽかーんとしているような状態なんですけれども、でもそこには何かがあって、それっていうのがすごく作品を作る上でも、大事なことなんじゃないだろうかというのを、今回すごいチャレンジさせてもらった展覧会の中で多く感じるところがありました。
- 荒井:
- 「あること ないこと」なんですけれども、結局やはり関係性の中での「あること ないこと」なのかなというのを改めて思いました。その中で僕の勝手な解釈ですけれども、デカルト的な近代自我というか、「我思う、ゆえに我あり」的な、そういう価値観がそろそろ煮詰まって来ているのではないかと思っております。
文化人類学を紐解くと、自我みたいなものがそもそも存在していないような集落が昔はあったりだとか、個というものないという考え方があったりするようです。
今回のPLANETという作品ですが、惑星は恒星があってその周りを回ってい流ので、まず恒星ありきで惑星は存在していて、さらに衛星がそこで回っているというような、関係性の中での存在ということを意識して作りました。
- 青木:
- 作品を作るうえでというか、美術と精神性という大前提のキーワードからお話ができないかなと思っていて、「あること ないこと」今回の展覧会もそうですけど、失われてしまったものというか、あったんだけどなくなってしまったことと、なくなったことに気づいていないこと、こういったものがいっぱいあると思うので、もう一回、拾い直す必要があるなと思うんですけれども、合理性だけではもう無理だという、さっきのお金のお話もそうですし、数字上だけのものでは全てを語れないし、補完できないということがわかってきてしまっているので、もう一度、忘れちゃったことというか、本来あったはずみたいなことを、取り戻すきっかけというか、そういったことが大事だと思います。
それは偶然とかいう確率的な話ではなくて、偶有というところで、出会い次第?ちょっと言葉が適切がどうかわからないですけれど、偶然性というより偶有性といったところで、もう一度浮上して来てもいいんじゃないかなという風に思います。
- ロジャー:
- 鈴木さんが今「見えていないもの」とおっしゃったこと、あるいは青木さんが「どう言葉にするか」とおっしゃったこと。その辺りの迷いというか、モヤモヤ感というのは作家と喋ったりすると、よく出てくるテーマです。「あること ないこと」から、私なりに改めて感じたことは、アートはそこのところと言葉とのネゴシエーション、会話が常に行われていなくてはいけないのではないかということです。それはみんなが感じたり見えたりするんだけど、どう言葉にするかという作業、出来にくい作業というか、そのマッピンングをする作業です。歴史的にみても時代によって違う言葉がそれを指すように聞こえますが、それがアートをやるものの使命でもあるとも思います。20世紀だけ見ても、スピリチュアル、崇高、超越だとか、いろいろな単語を美術学者、心理学者、人類学者たちが無意識に使ったり、60年代のサイケのムーブメントにいくと、それはサイケデリックという言葉が出てきたりもしました。私がやっている仕事というのは、まさにマッピングです。どこの領域を指すのかということを、アートに対していろいろな人がいろいろな言葉をそこに使ってきたわけです。それを一つの地図上にマッピングしていくというのは、ある意味ではずっとそこに関心があったのかなと思います。もしかして、実際に作っている作家たちに、なんらかの助けに少しはなれるかもしれないし、歴史的に、俯瞰的に見ていくことによって、「似たようなことを感じた」とか、作品作るときに、「ここはこういうことかな」と言うことができると思います。これは本当に、細かい作業で、いろいろな先輩方たちの言葉を読んだりすると、そこにも転がっていたりすることがあるんですね。アグネス・マーティンの日記を読むと、すごく素敵な詩で状態を表す能力もあったことがわかります。アボリジニーの、エミリー・ウングワレーの作品を見ると、また別の言葉でそれを言っているのを見つけます。その辺のマッピング作業みたいなものを改めて思い出しました。
- 藤井:
- 会場の方からご質問などございますか。……では、指名させていただきます。アーティストのピーター・マクドナルドさん、一言いただければ幸いです。
- ピーター:
- こんばんは。ロジャーの弟のピーター・マクドナルドです。青木さんとは、先ほど展示場所で会うことがあって、ゆっくり話をするチャンスがあって、それもすごい面白かったし、今晩こういう会で全員のアーティストの話を聞くチャンスもあって、先生の話も聞いて、考えさせられることがありました。また展覧会のこともそうなんですけれど、久しぶりに美大のスタジオに入って、生徒たちと喋る機会があって、それにもすごくエネルギーをもらった感じです。生徒たちに、ありがとうって言いたいですね。あまり今晩のシンポジウムの感想じゃなかったんですけど…。
- ロジャー:
- 彼はこの前ローマに3ヶ月住んだんですね。アンジェリコの作品も相当近くで見て、そこで感じたことがあったという話をしましたね。アンジェリコが生み出した文法…見えない世界とか、精神の世界を物質に変える文法を見事に生み出したアーティストとして。
- ピーター:
- 3ヶ月間、ローマに住むことができて、いろいろなイタリアの教会とか美術館に訪ねていって、アンジェリコとか、ドゥッチョとか、ルネッサンスのはじめの頃の絵を中心として、それらにフォーカスして見ていたんですけれど、なかなか言葉にできない…どうやってこれを話せるのかなっていうことをロジャーと話そうとしていました。見えないことというか、愛なのかもしれませんが、すごい力を絵から感じて、そういう面では今晩の話はすごい響きましたね。
- 藤井:
- もうお一人、アーティストの末永史尚さんにもコメントをいただきたく思います。
- 末永:
- お話を聞いていて、遊ぶというか、遊戯というか、そういうこともみなさんに共通しているかなという気がしていています。それぞれ真剣に制作しているんですけれども、展覧会場を使っていかに遊ぶか、制作を使って一緒にいかに遊ぶか、そういうところって結構作ることの根源なのかな、と感じました。真剣に遊ぶということってつまり、自分の方から積極的に行為に没頭し、楽しむことなので、社会のルールに合わせるのではなく、嘘がない。なんかそこが見えたのがとても面白かったです。
- 高橋:
- 話し出すともっといっぱい話すことはあると思うんです。ただ、皆さんのお話を聞いていて、一番こう感じたことというのは、もともととても抽象的な投げかけを僕はさせていただきました。それっていうのは、曖昧にしていくということではなくて、今回もそれぞれの作家さん一人ひとりを紐解いて言葉にしていった時には、それぞれ違う言葉、違う結論、違う価値観みたいなものにちゃんとたどり着くと思うんです。ただ、これからの時代というのは、一つの結論とか、一つの価値観で、そこでみんなが安心するというのではなく、先ほどからずっといろいろな形で話題に出ていると思うのですが、いろいろな価値観が提案されながら、その中でもっとすごく大きな目で世界を見ている。あるいはその、考えを考えているみたいなことがすごく重要だと思いますし、あるいは、それぞれのそういう価値観、あるいは、方法論みたいなものがお互いにすごくいいエネルギーになって刺激しあって、物事を解決していくみたいなことがすごく重要なんじゃないかなと、つくづく感じました。僕自身、キュレーターではありませんし、ひとりの作家として、自分が制作に落とす感じで、あるいは教える立場で考えながらやってきたことをとりあえずひとまとめにして、今回こういう展覧会を提案させていただきました。それで、それに対する3人の作家さんたち、十分に私の期待を超えるような作品を作っていただきましてありがとうございました。時間が差し迫っています。ありがとうございました。
- 藤井:
- 長時間に渡る議論をありがとうございました。