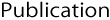CSP3シンポジウム「絵画と彫刻のあり方について」
モデレーター:石崎尚
参加者:堀由樹子、薄久保香、箱嶋泰美、中野浩二、大畑周平、鈴木友昌

<第1部>
- 石崎:
-
そろそろ時間になりましたので、CSP3のシンポジウムを始めたいと思います。みなさん、本日はお足元の悪い中、たくさんお越しいただきましてありがとうございます。私は本日のモデレーターを務めさせていただきます石崎です。今日は出品者の方々にご出席していただいていますが、中西さんのみご欠席です。その代わりに大畑さんがお話くださるということになっていますので、中西さんのコメント的なものはここで共有できると思います。まず、初めに作家さんのご紹介をさせていただきます。私に近い方から、堀さん、薄久保さん、箱嶋さん、中野さん、そして本日欠席されている中西さんの代わりに、お話くださる大畑さんです。そして、最後の1名はスカイプ経由でお話くださるロンドンの鈴木友昌さんです。
今日のシンポジウムは二部立てになっていまして、前半はまず、各作家さんに、作品をまじえながらお話をしていただく予定です。後半はここにいる全員でディスカッションを進めていくという二部構成になっています。それでは、よろしくお願いします。まず、第一部として作家さんに自分の作品を紹介していただきたいのですが、時間が限られていますので、一人あたり3点、もしくは多くても5点で、作品数を絞ったうえでお話してもらおうと思います。その際、いわゆる代表作というより、ご自身の作品のキャリアの転機になった作品のお話をしていただきたいということで、選んできていただきました。順番は、私から近い方で堀さんからお願いしてもよろしいでしょうか。
- 堀:
-
はい。
- 石崎:
-
堀さんの画像を見せながら、まず進めていきたいと思います。堀さん、1点目はどの作品にいたしましょうか?タイトルはありますか?
- 堀:
-
「WORK20003F」というタイトルです。これは、2000年の作品です。私は、東京造形大学を1994年に卒業しまして、卒業した時点では、版表現コースというところに属し、リトグラフを主に制作していました。リトグラフは、版を描いて作るという、とても特色ある版画なんですけれど、「描く」ということにすごくこだわって制作をしていました。その流れで、大学を出てからは、ドローイングをやったり、油彩をやったりという感じで過ごしていました。油絵を描き始めた頃は、もっと形のない感じの作品、タッチが画面に重なって、そのタッチの集積で、画面が動きのようなものを作り出すといった作品を作っていました。そういう感じで3、4年発表していました。そうした中で、タッチを重ねていくと、形態が見えてきたり、また消えていったりということがどうしても起きてきて、形態を見せていくのか、消していくのかということが、自分の中で問題になっていました。2000年頃に、形を積極的に残していこうということでやり出したのがこの作品です。
- 石崎:
-
ありがとうございます。では、2点目はどの作品にいたしましょうか?
- 堀:
-
こちらでお願いします。これも、同じ時期で、1年ぐらい違うかなという頃の作品なんですが、どんどん形を前面に出していく感じで作っていました。先ほどのも、F130号で、結構サイズは大きくて、縦194cm×横162cmという、私の背よりも少し大きいサイズです。ですので、自分が動きながら画面に寄っていって、絵の具をつけて、また引いて画面を見るというような、体を使って描くというサイズのものです。これは、遊歩道を描いています。左側に街路樹が並んでいて、右側にずーっと伸びているおだんごのようなものは、その街路樹の影というのが、自分がイメージしているものです。ただ、このように見て欲しいというよりは画面としてのおもしろさを出したいなと思ってできた作品です。
- 石崎:
-
ありがとうございました。では、3点目はどうしましょうか?
- 堀:
-
こちらでお願いします。これは、2015年のものです。筆跡を重ねて形が見え隠れするということをやっていたところから、先ほどのように形をしっかり見せていくという方向で進んでいます。モチーフは、ずーっと、いつも日常の中で接している風景だったり目にするものの形です。これも、今私が住んでいる家の向かい側が森のようになっていまして、それを写生しているわけではないのですが、思い浮かべながら描いたものです。この作品は、F20号が3点並んでいるのですが、想定としては、窓の外みたいな感じで、余白は窓の桟みたいなことを想定して作っています。ただ、必ずしもそういう風にして見て下さいということではなく、一応3点組の状態でこういう一つの作品ということでやっています。これが今やっていることです。
- 石崎:
-
どうもありがとうございました。ご自身の作品を3点、要領よくまとめていただきました。どうもありがとうございました。次は、隣の薄久保さんの作品を見ながら進めていきたいと思います。まず1点目はどの作品にいたしましょうか?
- 薄久保:
-
2012年あたりのシリーズから紹介していきたいと思います。私にとって描くということは、この世界の謎にせまるということです。それが何であるかということを自分で知りたいということ。「絶対的な何か」に触れるということが絵を描くこと、という風に考えています。もともと絵画科を卒業してすぐ、CGを制作する会社で少しの間働いていたんですけれど、そこからもう一度、絵を描きたいなと思って、東京芸大の大学院に進学しました。そこから、自分にとって絵画というものは何なのか、という一つの問いに対して正面から向き合うことになったのですが、この作品はその始まりの時期のものです。
私は、CGを駆使してリアリティのある視覚媒体をつくるという仕事をしていたのですが、それまでの私は手で触って絵の具を使ってものを作っていたわけです。そうした経験から、人間にとってのリアリティとか、この世界の成り立ちというのは何だろうということを、今振り返ると、この頃漠然と考えていたのではないかと思います。そして、そういったとき、いつも私の中に出てくるものは、二項対立のようなものだったんですね。現実と虚構であったりとか、実在と非実在であったりとか、創造していくことと非創造、破壊なのか生成なのかというようなこと。最近も宇宙の成り立ちについていろいろ話がされていると思うんですけど、物質と反物質とか。この世界にはなぜ両義性をもった言葉やものが存在するのかというようなことが、自覚的ではないですけれども、すごく気になっていました。
この当時は3Dで作ったものと、視覚的に見えるなにかなのかわからないですけど、そういったものと、実在するもの。そういうものを混ぜたような作品を作っていました。この女の子は実在する子で、撮影をして、そして背景の荒涼とした大地は、コンピュータグラフィック上で作って、この世界には存在していないものです。私の中では、人物も他のオブジェクトも優劣関係がほとんどなくて、両方とも対等に、平等に扱われるオブジェクトです。私たちがよく知っている、触れられる人間というものと、CGでできた舞台というものをもう一度絵の中に落とし込んだ作品です。
これはもともと震災が起こる少し前にプランを考えて描き始めて、震災の頃にちょうど描いていたものなんですけれど、「予言の証明」というタイトルです。予言って結構不思議なものじゃないですか。未来のことがわかるのかわからないのか、わからないけど、まだ起きていないということについて語られるという、その時間を考えたときに、まだ起きていないのに真実のように述べられる。こういうことが起きるということが、本当にあるのかないのかという。時間というものも、すごく不思議なもので、ある種両義性を持っていますよね。ある瞬間はとても長く感じたり、ある瞬間は長い時間が経過しているんだけど、短くなってしまったりとかという。私たちが生きていくうえで、とても興味深いテーマなので扱いたいなと思っていました。ただ、絵を描くことと現実に起きたことというのが、あまりにも自分にとっては、生々しいくらいリンクしてしまったシリーズで…。
- 石崎:
-
リンクしてしまったというのは、これを描いていたのは、震災前だけれども…ということですか。
- 薄久保:
-
そうなんですよね。実際そういうことを想定していたわけではないんですけれども、日常の中でいつか不条理な出来事が起きてしまうと言われるようなこと、不条理な出来事というか、そういうものがあるということを私たちは知っているけれども、それが実際に起きるまで私たちは生々しく感じることはできないので、「予言が証明されてしまう瞬間」、という意味でこれを挙げました。
- 石崎:
-
この作品で、これまでの作品観というものを結構お話くださいましたので、この1点に代表して、次に箱嶋さんにお願いしたいと思います。箱嶋さん、1点目はどれにしましょうか?
- 箱嶋:
-
入っている順番でお願いします。私は、幼いときに父の仕事の都合でタイのバンコクに住んでいたことがあるのですが、造形大学に入学して自分の制作を進めていくうちに、ちょっと自分の制作ってなんだろうというのを振り返ってみたいと思って、だんだん考えていくうちに、一度幼い頃に育った場所に戻ってみたいというのがありまして、造形大学を卒業してから2年間、バンコクのシラパコーン大学という美術大学があるのですが、そこに留学とレジデンスで行き、制作を行いました。そのあともアジアを取材して描くことが多いのですが、この絵は留学期間中に訪れたスリランカ(ちょうど父がその頃赴任していました)のコロンボというところで見た風景を描いたものです。この作品は、毎朝、部屋の窓から下をのぞくと、知らないおじさんが同じ時間にバシャバシャ泳いでいて、なかなか前に進まなくておぼれそうになっているというところを描いたものです。その人その人が持っているスタイルというか、生き方とかがとても魅力的というか、私にとって描きたいものになることが多いです。この作品は、描きたい画面の大きさとか構成とかがしっくりきたんだなと後で振り返って思ったので、選びました。
- 石崎:
-
ありがとうございます。2点目は、こちらでいいですか?
- 箱嶋:
-
はい。これは、おばさんの後ろ姿なんですが、タイのバスの中で見た方です。知り合いではないのですが、気になったものはその場でスケッチをしてスタジオに持って帰って制作するというスタイルでやってきていて、今もそれに近いのですが、そうしたスタイルになる初期の頃です。正面から見ると失礼かなと思って、後ろ姿を描くことがこの頃は多かったです。
次の作品をお願いします。これは、日本に帰ってから築地で見た魚河岸のおじさんなんですが、初めて正面からしっかり描いてみたという作品です。
次お願いします。これは、またちょっと違うんですけど、バリのホテルのロビーにいた、リゾートコンシェルジュという、ホテルの観光案内係の方です。この方はとても熱心にバリの良さをお話くださって、部屋で流れているプロモーションビデオにもこの方が出演して、バリを熱く語っている。ここの雰囲気も含めて描きたいなと思ったのと、あと、広い空間を描くというのが自分にとってとても難しくて、それを初めてやってみようと思って描いた作品です。
次の作品は、去年の作品です。ベトナムのホーチミンなんですが、透明なプールがあって、下と上に泳いでいる人がいるんですけど、街の様子と、喧噪から離れて深夜泳いでいる人を描いたものです。
- 石崎:
-
ありがとうございます。だいたい異国の地で見たものを描くことが多いのですか?
- 箱嶋:
-
日本のものも描くのですが、自分の原体験から影響しているのかわからないのですが、あまり洗練されていない場所で描きたいものが見つかることが多いです。
- 石崎:
-
日本でも魚河岸みたいなどちらかというとスタイリッシュではない場所に行って取材されることが多いのでしょうか?
- 箱嶋:
-
狙ってそれをしているわけではないのですが、例えばど派手な大阪のおばちゃんとかを描いたらどうかと言われるのですが、その中でも描きたい場合と、描く対象にはならない微妙なラインがありまして…。東南アジアに興味はあるんですけれども…。
- 石崎:
-
ありがとうございました。次は、中野さんの作品を紹介したいと思います。
- 中野:
-
僕は人物をずっとモチーフにして彫刻を作っています。卒業してから木彫で具体的な人の体でなにかできないかと思い、制作をしていました。その中で、なにか、こりっとした作品を作りたいと思って素材の違うものを組み合わせて作ったりしていたのですが、どうもうまくいかないなと思って…。もっとシンプルに人の形を作りたい、ということだけでいいんじゃないかなと思って、大学時代に学んでいた首像があるなと思ったんです。それで「首」に集中して制作しようと思い、先ほどの石膏の像になりました。これは、最初粘土で制作をして、それを石膏で型を取ったんですけれど、全然うまくいかなくて…。そのときに型どりした雌の方ができるんですけど、その雌だけが残っていて、もう一回、布を石膏にまぶしたものをその型に入れて、割り出してみたんですね。そしたら、脳みそのような生々しい形が出てきて…。僕がイライラしてばしゃってやったという、そういう形もすごくそのまま形に写っているような感じがして、僕にはすごく魅力的な形に見えたんです。そこから急いでそのまま歯を付けたり、あごの部分を詰めたりしました。型をとったときは、最初顔の側面や後頭部などの部分が出てきて。あまり細かいことはできないんですけれど、それがすごく僕にとっては良くて…。「これでもいいのかな」と。僕にとってリアリティのある作り方になったなと思いました。
- 石崎:
-
まさにこの作品で達成されたということですね。二点目はどれにしましょうか?
- 中野:
-
この作品でお願いします。首像の作品になってから、素材もいろいろなものを自由に使うようになってきて、アトリエもどんどんせまくなってきたんですね。それで、ここにとどまるのがいやで、もっと大きいのが作りたいなと思って。首だけではなくて全身像も作れないかなと思って作ったのがこれです。
次の作品は、最近のものです。もう一回、全身像を作りたいなと思って、作ったものです。4メートル半ぐらいあります。
- 石崎:
-
どうもありがとうございました。次は大畑さんですね。
- 大畑:
-
CSP実行委員の大畑です。中西さんが仕事で出席できないということで、私と中西さんは大学の同級生ということもあって、彼が大学のときにしていたことはわかるんですけど、その後卒業して京都の大学に行って、そこからかなり作品が変化していきました。中西さん自身は、彫刻という自覚を持って作品を作っていて、実際それは、写真のレイアウトを重ねていくように、写し出しているんですけど…。左が森を写した写真と、日が昇るときの写真。右側の方は、日が昇るところで、1時間半くらい定点でひたすら写真を撮っていったものの集積です。左は、彼が三歩ごとに写真を撮っていったものが映し出されています。時間の流れとしてはちゃんとあるんですけど、その間に彼自身が雲の動きとか、いろいろな流れの中で選び出した並びになっています。この作品のおもしろいところは、正面から見るとなんとなく平面的なんですけど、斜めになると立体的なものに変わって、真横から見ると、作品が放射状に目に映ってくる。そういう体験を通して、作品の中に入り込んだり出て行ったりということをひたすらくり返していくうちに、なんらかの体験を共有させようという試みがあります。彫刻というのは、彼自身は、時間がどう係わっていくかということをすごく重要視しているようです。実際この作品全体を見るためには、あらゆる角度から見ていくということを必要としています。
テキストにも、ちょっと書いてあるんですけど、ミケランジェロに『奴隷』という作品があります。その作品には、明らかに奴隷が苦しんでいるような人体の形もあれば、ものすごく粗々しく岩肌が残っているものもある。そういうところで、作品を見るときに、作り手の目線から見ると、岩からノミ跡とかから、作品がどういう風に掘り出されたかということがわかったり、逆に奴隷の形の方を見ると、奴隷自身の痛みに変わっていくとか…。同じものでも、ものが変化していくということをかなり意識して作っている作家だと思います。
- 石崎:
-
大畑さん、ご自身の作品ではないのにどうもありがとうございました。次は、ロンドンの鈴木さんにお話をうかがってみたいと思います。鈴木さん、聞こえますでしょうか?
- 鈴木:
-
はい、大丈夫です。
- 石崎:
-
鈴木さんにも3点ぐらい、ご自分の転機となった作品を画像とともに紹介していただきたいと思います。
- 鈴木:
-
転機になったのは、今考えて見ると、この「ジャパニーズビジネスマン
というタイトルの作品です。父親の彫刻を、1995年の大学4年生の卒業制作のときに作ったものです。これが初めて、木に色を塗った彫刻で、それまでは、こうした人体制作をやっていました。4年間造形大学で彫刻を勉強していて、初めて木で作ったのがこの作品です。当時、彫刻科には舟越桂先生がいて、先生の影響を受けて、木に彫刻をする作品が、学生の中には多かったんですけど、僕も影響を受けた一人だと思います。その時に展示した作品が、コンクリートの団地の彫刻を作って、そこに今お見せした「ジャパニーズビジネスマン」の彫刻を置いたんですけど、これが初めて、自分の言いたいことがちょっと言えたかなという彫刻です。
そのあとに、ロンドンに留学しました。1998年にゴールドスミスカレッジのサティフィケイトコースに留学したのですが、大学の授業内容が、1週間に1個作品を作りなさいというかなり早いペースで、年間何十個も小さいオブジェを作らなければならず、こうした作品を作りました。 これは人なんですけど、人がメガネをなくして探しているという作品です。このときは、留学したばかりで何を作っていいのかわからなくて、とりあえず、頭に浮かんでくるものを作り続けただけでした。でも、なかなかアイデアが浮かばなかったという経験が、逆に良かったかなというか…。そのあとに、今の作風の元となる彫刻ができあがりました。造形大で先ほどの父親の彫刻を作って、それから、一度自己解体したというか、一回、何がやりたいかというのを見つめ直したときがあったんです。この作品は、ロンドンで今やっている木彫の原型になったものなんですけど、この作品に到達するまでに、一度、大きなギャップがあったということが、自分の中で大事だったなと。
さっき見ていた、電信柱にぶらさがっている人の作品がありましたよね。ゴールドスミソニアンカレッジは、ダミアン・ハーストとか、コンセプチュアルアートがものすごく盛んで、僕もそれに憧れて、具象彫刻を一回あきらめようと思っていたんです。それでも、いざ何かを作り始めると、具象彫刻が出てきてしまうという雰囲気があって、結局やめようと思ったんだけど、やめられなかったんです。そう考えると、この作品はとても大切な作品だったなという。
- 石崎:
-
どうもありがとうございました。みなさんに作品の概要を説明していただきましたので、きりがいいところで10分間ほど間に休憩をはさませていただきます。16時25分から第二部のディスカッションを始めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
<第二部>

- 石崎:
-
それでは第二部を始めたいと思います。第二部では、作家さんを交えてディスカッションを進めていきたいと思います。今回の展覧会のテーマは「絵画と彫刻のあり方」というやや大きなテーマになっています。絵画も彫刻も、非常に歴史の長いジャンルでして、それを踏まえた上で今回の出品作家の方々が選ばれていると思います。また、展覧会をご覧になった方はおわかりのように、絵画、彫刻、それぞれ3名ずつ、みなさんどれもがひと言で言えば具体的なイメージのある作品ということです。一つは具象という点、もう一つはどちらも長い歴史を経たジャンルであるということを私から事前に出品作家の方々にいくつか質問をしましたので、その質問と答えのやりとりをしながら進めていきたいと思います。
質問の一つ目は、絵画や彫刻は非常に長い歴史のあるジャンルなんですが、その歴史そのものを意識するのはどういう点ですか? あるいは自分の制作がその歴史とつながっていると思うのはどのような点ですか?という投げかけです。それについて、みなさん、いろいろ考えていただいたと思うので、堀さんから聞かせていただいていいでしょうか?
- 堀:
-
はい。人間がもともと持っている原初的な欲求として、何か形を描いたりだとか、跡を付けたりだとかということがあると思うので、私も絵を描きたいモチーフに出会ったときに、描きたいという衝動が沸くということは、人間が持っている感情としてあるんじゃないかなと思います。それと、今歴史に残っているいろいろな作品を見ること自体も好きなので、いろいろな作品から触発されたりすることはよくあります。100年も200年も前の人が描いた作品を目の当たりにしたとき、絵の具の重なり具合であったり、こういう筆でこういう風に色を塗ったのかなとか、この色とこの色をこう混ぜて塗ったんじゃないかなとか、本物の絵の具で描かれた作品を目の前にしたときに、すごくリアルにイメージできたりすることがあります。それは時代も、生まれた場所も全然違っている作家の作品を見たときにそういうことが起きるということは、絵を描いたり見たりすることのすごく不思議なところ、魅力であるんじゃないかなという点で、歴史を意識することはあります。
- 石崎:
-
昔の人の作品を見るときは、描いているところを追体験しながら作品を見ているということが多いのでしょうか?
- 堀:
-
それを意識的にやっているわけではなく、好きな感じの作品と、あまりぴんとこない作品はもちろんあります。しばらく見ているうちに、なんとなくイメージができるものは、足を止めてじっくり見てしまって、思い込みかもしれないですが、その絵描きになりきって見ているということはあります。
- 石崎:
-
第一部で堀さんが最初に見せてくれた作品の中で、タッチを重ねて、形が出てくるか出てこないかのせめぎ合いがあるとおっしゃっていましたね。さっきおっしゃっていた人間のすごく昔からある形を残したいという衝動を、あの頃の作品のちょっと前までは、どちらかというと抑えていたという部分はあるのでしょうか?
- 堀:
-
むしろ形態よりもタッチを残したいというようなことがあったので、抑えていたということはあまりありません。ただ、ちょうど私が発表し始めた頃は、1995年頃かもうちょっと後なんですけれども、「絵画」とはあまり言っていなくて、「平面」という言い方をしていたんです。なにか形象を描くということが、あまり正面切ってできないみたいな雰囲気があって…。今の学生さんはよくわからないと思うのですが、具象的な絵画はちょっと違うという雰囲気があって、そこで育っているので、その中から形ができてきちゃうんだけど、出すのか出さないのか…、形が出てくるとその形の意味も自分に問うてしまうので、その辺の整理がつかないまま何年かタッチを重ねていたということはあると思います。
- 石崎:
-
そのあと、今のようにいろいろな形が自由に出てくるようになった、整理がついたきっかけというのは何ですか?
- 堀:
-
それは多分、記憶がはっきりしないんですけど、1997年頃に文化村でボナール展をやっていたときだと思うんです。ボナールはすごく好きなんですけど、自分は形象を描くか描かないかみたいな悩みを抱えながら展示を見て回っていました。そんな中、ボナールの幸せいっぱいの画面を見たとき…、例えば、食卓であったり自分の奥さんであったり、果物とか…。そうした形態をこんなに幸せそうに描けるんだなということを認識して、改めて「ああ、絵ってこうだよな」と思いました。やはり、「形を描くということが絵だよな」ということで少し開き直れて、それで先ほどの形を見せていくという方向になったんです。
- 石崎:
-
ありがとうございました。次に同じ質問に対する薄久保さんの考え方をお聞かせいただければと思います。
- 薄久保:
-
このお題をいただいたときに、どの部分の話をしようか結構考えました。美術史的な問題と、私の作品がどう接続しているのかしていないのかという部分を答えようかなと最初思ったのですけれど。そもそも私の作品の中に意識するとか意識とは何かという、先ほどの話の続きにもなるんですが、一般的な暮らしの中で、「私」というものが世界をどう捉えているかということに話が発展していくのかなと思います。そういうものの捉え方の方を考えてしまって…。もちろん絵画や彫刻をやっていて歴史となにかしらの接続をしていないということはありえないわけですよね。もし「ない」と言ったとしても無自覚なだけで絶対に関係してしまっています。
最初に、「世界」を把握するために、「絶対的なもの」という言葉を使ったんですけれど、絶対的なものというのは何をもって作品化されるかということにもつながっていきます。作品って、単純な「我」とか、本能的な欲求だけでも作れないし、かといって理性的論理的な道筋立てをすることだけによっても、絶対的なものに触れるという境地に立つことは不可能だと考えています。それはなんなのかというと、ある種、「我」を排除した自覚的に自分を意識しなくなるような境地に到達できるような次元と考えています。私は1年前から京都に住んでいます。京都には、陶芸家の河井寬次郎記念館がありまして、私はそこがとても好きなんです。そこに、河井寬次郎が書いた言葉があって、とても印象に残っています。それが、「鳥が選んだ枝、枝が待っていた鳥」という言葉です。それを読んだときに、この世界の成り立ちの全てをこんな短いひと言で表現できるんだって思ったんです。悟りの境地のようなものを感じました。もし鳥を私たち人間になぞらえるのだとすれば、私たちが歴史を意識するとか、キャンバスを選んでいるとか、今日こういうものを食べようとか、私側からの話というように。もちろん人間は「私」の中から出られないし、毎日「私」というものをやっているんだけれど、本当はそうじゃなくて、頑張って主体的に選ぶとか、考えるとか努力するとかということ以上に、この世界の中に自然なめぐりあわせの法則みたいなものがあるんじゃないかなという。例えば、椅子が座られるのを待っているとか、そういったような部分というか、私が選んでいるのではないような法則。これがスピリチュアルな話みたいになってしまうとちょっと違ってしまい、私は作家としてそういうことは、真剣に考えなければいけない部分なのではないかと考えていますね。
3つの作品、さっきご紹介できなかったんですけれども、結構最近の転機みたいなのは、去年今年にかけて作っているコラージュを介した作品なんです。今回出品した作品もコラージュが元になっていて。最近の自分の興味は、私がこうしたいとか、私が私が、みたいな「我」の部分ではなくて、どうやったら自分を排除した世界を作れるのか、見られるのか、少しでも触れられるのかみたいなところにあります。そういう意味ではキーワードとしては、美術的にも接続できるポイントというのはあるのですけれども、どちらかというとリアルな体験のほうからお話させていただきました。
- 石崎:
-
今、話していただいた「鳥の選んだ枝、枝の待っていた鳥」に関して言えば、薄久保さんの場合は、自分の描きたい絵というよりは、絵が待っていたような絵を描きたいというようなところがあるんですか?
- 薄久保:
-
そういう部分はあります。私が選んだという人間中心的な「おごり」みたいなところからどう脱せるか。でも、そうはいっても人間だし、「我」も、もちろんあるわけであって、そのどっちつかずの部分にあるところにさっき言ったような境地やフィールドがあって、それを私は絵画という中に捕まえていっているんじゃないか…と。私が捕まえてるの? それとも私が捕まえられちゃってるの? みたいなことは結構考えます。
- 石崎:
-
そういう思いを抱くにいたったのは、さっき見せていただいた絵が、図らずも震災とシンクロしてしまったことというのは大きな影響があるんでしょうか?
- 薄久保:
-
実体験もあるのですが、日本の近現代の思想とか哲学というものがもともと気にはなっていたのです。それで、京都に引っ越してから特に本を読む機会が多かったので、このように考える部分も大きいのかなと思います。自分がやっていることがなんなのかとか、なぜ二つに分けられてしまうことに興味があるのかとか。でも、最終的には分かれていなくて…。私は最初は分かれているんじゃないかなと当たり前のように思っていたんですよ。表があって裏があってとか、現実があって虚構があってとか。小さい頃から何か二つの要素に分かれているって思い込んでいたんだけれども、それはいつも一緒で、私という主体が環境を作っている側面もあるし、環境というものが、私を作っているという関係性、さっきの河井さんの言葉に集約されることなのかなというところで、そういう意味では美術を意識するという言葉自体に少し反応していた部分というのはありましたね。
- 石崎:
-
ありがとうございます。次は、隣の箱嶋さん、同じくお聞かせいただけますか?
- 箱嶋:
-
私は、率直に言うと、自分の制作をする上では、絵画の歴史を意識することはあまりないのですが、堀さんもおっしゃっていたように、例えば美術館に行って歴史上の名画を見たりするときに自分の好みというか、自分が好きな絵の具の重なり具合や塗り具合であったり、色の配置とかを見て共通点を感じることはあります。ただ、制作する上で歴史をというと、あまり意識的にすることはないです。
- 石崎:
-
私がこの質問をした意図の中には、例えば画家がキャンバスに向かって何かを描こうとしたときに、真っ白な中に何かを描こうとしても「すでにこれは歴史上描かれてしまっている」、「さんざん今までにされてしまっている」ということが少なくないんじゃないかなということがあります。では、一人の画家として、どうやってそうではない作品を作ろうとして向き合っているのかなという疑問もあって、この質問をさせてもらいました。
- 箱嶋:
-
大学時代から、もうすでにあるような作品じゃないものをというのは、みなさん意識的にやっていらっしゃる方が多いと思うのですが、私の場合は、油絵を描き始めたのが中学生の時からでして、それまで絵を描くのが好きというわけではなくて、油絵の具という物質に触れたときにすごく表現しやすいというか、しっくりきたので、続けて美術大学に入りました。大学に入ってからいろいろ勉強したり先生に教えていただいたりするうちに工業製品というか、できている色と絵の具を使ってできているものに描く、ということに少し疑問を感じた時期があって。学生時代は紙をすいたり、染色してみたり、わけがわからない物体を作ってみたりという遠回りをしながら、結局自分が何をしたいかというのを考え続けていました。そうしたら、やはり油絵の具で描くということだなと。では、油絵の具でなにが描きたいかというと、どういうものを見て、どこに行ってどういう人に会って、それをどういう風に描きたいかというところが重要だと思ったんです。それが結果的に誰か他の人の絵に似てしまっていても、今はそこまで考える余裕がないというか、結果的に誰も見たことのないような絵になればそれはそれでいいと思うんですけど…。
近代絵画以降、みなさん新しいことをやってきてはいるけれども、似ているものというのはたくさんあるので、そこをあまり私は重要視していないといったら変ですけど、今のところあまり意識にはないです。
- 石崎:
-
どうもありがとうございました。次は中野さんにうかがってみたいと思います。よろしくお願いします。
- 中野:
-
僕は、人物像というか具象で、ずっと、大学では粘土で裸の像を作ってそれを石膏にとってということをやっていました。卒業後も人物をモチーフにずっと制作していて…。学生のときから、人の形を作って意味があるのかということを結構周りにも言われるし、今やる意味があるんだろうかといつも自分でも考えます。僕は人によっては粘土でブロンズにしている裸の像ということでも、今でもやれる人はやれるんじゃないかと思っているし、それでもいいんじゃないかと思っています。ただ、僕はそれではうまくいかなくて。
日本人が彫刻を学んだ環境というのはどういうものだったのかなと思うと、明治頃に急に入ってきたもので、それは多分その当時、全体的に近代化していくうえで意味があることで、みんな頑張ってやったんだと思うんです。ただ、今の僕がそのままやっても違うなと思っていて、もう少し身近な部分で素材の選び方や作り方を考えていかなきゃいけないんだなと思って、さっき見せたような石膏の作品になっていったのです。その時、瞬間的にぱっと形ができあがったときに、イライラしたり、投げただけでできた形を見たとき、今の僕そのものがうつったというイメージがすごくあって、それは今生きている僕の自刻像という意識がなんとなくありました。だったら、こういう風に人の形で作ってもいいんじゃないかなと思えたんです。
- 石崎:
-
ありがとうございます。今、中野さんがおっしゃった「今どき人体作って何の意味がある?」という当時の周りの印象というのは、さっき堀さんに話していただいた今どき具象やってどうするの?」みたいな学生時代の空気とやっぱり似ていると思うんですね。お二人は全くの同級生というわけではないですけれど、90年代半ばから2000年頃に大学を卒業した人の中にはやはり、どこかでそういう、「作りたいものを作ろうとしたときに抑圧される周りの雰囲気」って確かにあった気がするんですね。中野さんは、いわゆるブロンズ彫刻ではない方向で、人体とか首像を追究されていくわけですけど、そういう風に思うきっかけって何かあったんですか? それは、さっき見せていただいた頭蓋骨みたいなのが出てきたときがそうなんですか?
- 中野:
-
僕がそのまま写ったという気がすごくして、今の僕が作っているんだということで、「あってもいいな」と思いました。
- 石崎:
-
むしゃくしゃしてあれを投げ捨てて良かったですね。
- 中野:
-
そうですね。
- 石崎:
-
あれがなかったら今頃どうなっていたんだろうという感じですよね?
- 中野:
-
あのとき使ったのは、医療用の包帯石膏というものだったんです。それは、今回出品されている中西さんから学生のときにもらったものだったんですね。だから中西さんのおかげなんですけど。
- 石崎:
-
意外な作家同士のつながりが見えておもしろいですね。では、次はロンドンの鈴木さんにお話を聞いてみたいと思います。鈴木さんご自身が、彫刻の歴史を意識したり、自分の作品が歴史とつながっているなと思う部分はありますか?
- 鈴木:
-
今みんなの話を聞いていてすごく共感する部分があります。今僕はロンドンにいるので、大英博物館に行けば、自分が歴史につながっているんだと思うし、学べることはたくさんあるけど、やりつくされて何やっていいかわからなくなる自分もいます。さらに現代では3Dプリンターが発達して、さらに具象では何をやっていいかわからないところにきてしまっています。
じゃあどうしたらいいかってなったときに、「びびらない」。それしかないと思うんですよ。とにかくびびらないで、耐えるというか。なにをつくっても、なにかに似てしまうかもしれないし、テクノロジーには負けてしまうかもしれない。でもとにかく、びびらないで、やっていくしかないなと思います。
- 石崎:
-
ありがとうございます。「びびらない」ということを言えるようになるまでには、鈴木さんの今までのキャリアの中で自信になっている部分が蓄積されているということがあるからではないかと思うのですが、鈴木さんのそうした信念を支えているのは、今までの人から受けた評価とかが自信の元になっているんでしょうか? それとも違う部分でなにか支えてくれるものがあるんでしょうか?
- 鈴木:
-
びびってるからびびらないように、というそれだけです。彫刻とか絵画は一番歴史が古く、現代のニューメディア、ビデオインスタレーションとか、いろいろなものがあるなかで、個性を出さなければならなくなっています。そうなってくると、さらにびびってしまうので、なるべくあまり周りの意見に振り回されないようにしようとしているのが、今の自分なのかなと。
- 石崎:
-
さっき中野さんに聞いた質問と似ているんですけれども、鈴木さんがハーストかぶれのコンセプチュアルアートをやりたいと思ったときに、それでも作っていると具象とか、人間の体が出てきてしまうとおっしゃっていたじゃないですか。じゃあ、人間の体が出てきてもいいじゃないと思ったきっかけとかあるんですか?
- 鈴木:
-
ハーストが大好きでゴールドスミスに入ったんです。やはり、とてもかっこよかったから…。でも、ポール・モリソンという僕のチューターから、「今更ダミアンやってもしょうがないよ」、「遅いよ」って言われました。ものすごい勢いでこちらはコンセプチュアルアートが進んでいますから、今ここで僕がやったところでどうにもならないよって言われたのがきっかけで、もう一度、造形大学で習ったことを見直しました。コンセプチュアルな流れが強いイギリスで、いかに自分の作品のアイデンティティを見せるか、人と違うことをやれるか。逆に言うと、マイノリティーな具象彫刻のほうが、逆に有利だったのかなと思います。
- 石崎:
-
今のお話には意外なおもしろさがありまして、今日本の美術大学の教育は、結構欧米に倣えというようなところがあって、海外の大学と連携して、教育内容もそういう風にしようみたいな流れがあります。でも、鈴木さんは一人でイギリスに行って、自分ならではのものを探したときに、結局4年間日本の造形大学で学んだ人体彫刻に立ち戻ったという。今の日本の作家は海外とどう勝負すればいいのかというのを、すごく悩むと思うんですけど、鈴木さんの話からすると、意外なところにヒントがあるんじゃないかと思いますね。
- 鈴木:
-
そうですね。だから、はっきり言うと、どの大学も似たり寄ったりで、イギリスの美術大学もそうだし、アメリカもそうです。でも、その中で特に造形大学の彫刻科は古くさいと言われていて、逆に考えたらその中で育った少人数の人たちが一番ユニークになっているわけですよ。1年生のときに石を削らされて、頭部を作らされて、道具まで作るという教育はどの大学でも教えていない。そういう面倒なことはやらせないんです。だから、すでにその大学に入った時点で、ユニークな存在になっているはずなんですよ。他がみんな今、似たり寄ったりの教育というか、ボーダレスにいろいろなものが交じってきていて、分化がなくなってきているので。
もちろん取り入れたものは取り入れたほうがいいし、大学の提携もしたほうがいいと思うけど、本当のユニークさという点でそれがユニークな大学になっていくかどうかという風には、僕は思わないですね。
- 石崎:
-
今、本当のユニークさという言葉があったんですけど、かといって、鈴木さんが4年間造形大学で学んだことをそのまま出していたら、今の作品はないじゃないですか。やはり木彫の技術と、ある種のストリートカルチャーというような人体表現の合体があって初めて今の作風が生まれていますよね。それは、村上隆さんが、海外とどう勝負するかというときに、自分の持っている日本絵画の平面性とオタクカルチャーを合体させれば、海外でも勝負できるんじゃないかという戦略に到ったということと、似たような戦略の立て方は、鈴木さんの中にあったんですか?
- 鈴木:
-
ゴールドスミスに行って学んだことはコンセプチュアルアートがベースでした。造形大学から行って、とても不得意な部分を学んだというか、油と水みたいな違いがあったんですね。村上隆さんもおそらくニューヨークに留学しているはずだし、一度海外に行って、日本をもう一回見ているという作家、奈良さんも草間さんもそうだと思います。一回外に出て、何か気がつくというきっかけがあったんじゃないかなと僕は思います。大竹伸朗さんも留学しているし。共通するのは、技術は日本で蓄えているけど、海外に出ているということなんです。やはり僕は、一度は海外に出てみるべきだと思います。
石崎:非常に説得力のあるお話をありがとうございました。今だいたいみなさんのお話をうかがって、それぞれの作品の背景というか作家としての立ち位置というのも理解できたんじゃないかなと思います。次は、この展覧会、せっかく優れた作家さんを招いたグループ展なので、今度は自分の作品からちょっと離れて、他の出品作家さんの作品について興味があることとか、質問などがあればお聞きしたいと思っています。また堀さんからお聞かせ願っていいですか?
- 堀:
-
私は絵のことにやはり興味があるので、薄久保さんと箱嶋さんお二人にうかがいたいと思います。私は、ちらっと先ほどお話しましたけれど、リトグラフを作っていましたので、まずエスキースがあって、エスキースと作品の関係みたいな。版画を作る場合、ある程度の完成型がエスキースとして固まっていないと作品にならないんですけど、そこが私は非常にきつくて、本当に描きながら決めていくみたいな、そういう方法が今すごく強くなっています。薄久保さんと箱嶋さんは、ある程度の完成型を思い浮かべてスタートするのか、ゆるいところでエスキースを作っているのかをうかがいたいです。
- 箱嶋:
-
私は描きたい人とか風景を見つけたとき、その場でメモなりスケッチをすることが多いのですが、その時点でだいたい何を使ってどういう色でどのくらいの大きさで描くかというのがしっくりいけばうまくいくし、それがあいまいなままでいくと、画面がどろどろしてしまうことがあります。かといって決まりすぎてて、簡潔に終わってちょっと違ったなということも…。でも、どちらかというと先に決まっていて、そこを目指して描いていくというタイプです。始めに持っていた描く人の印象が、ここまで描きたいというのが出せたところで終わりです。
- 薄久保:
-
話は連続していきますが、「私」が決めるのかという部分にまた入ってくのですけど、モデルさんを撮影したり、オブジェを作ったり、コラージュなんかをしている過程で、イメージというものが、徐々に生成したり突然生成されていったりします。最初の時点では、どうなるか全然わからないです。ある種のめぐりあわせのおもしろさみたいなのが重要なのです。オブジェにしても「私が作る」というようなことよりも、例えば、夫が何か買ってきたものであったり、友だちがくれたものとか、今ごみとして捨てられそうになったものであったりとか。偶然性ってすごいなあと。偶然性の驚異と法則。自分という「我」を超えるチャンスがそこにはすごくあるんです。そういう意味では、一番最初の時点では、完成のイメージはないです。作品をご覧いただくとわかるように、そういうオブジェとかコラージュをそのまま作品として表には出してはいません。そこは、みなさんが話していた、どういうものにも可能性はあるというところで、私は「好き」っていうことって、哲学的にも深い問題だと思うんです。これはみなさんが作品を作っている上での根源的な動機だと思うんです。「好き」っていうことの奥深さ。「好き」って、スポーツでもゾーン状態とかがありますが、スーパー集中力状態ともいえます。「好き」っていうことは、絵を描くときは絶対的に必用なんです。ただ、もう一つ理想的な方向性の方で言うと、私にとってオブジェのままであるとか、コラージュのままであるというのは、あまりにも現実のそのまますぎて、現実にすぐさま引き戻されてしまう感じがある。それを、写真に撮って、もう一度絵にするというプロセスとしては一見遠回りのような気がしますが…。まず写真のおもしろさは、事実の重要性を客観的にありのままに、非個性的に映し出すところがいいなと思っているんです。ただその時点では写真のままでもいいのかもしれないけど、絵で描いた質のほうが違和感があっていいなと思っているんです。今後プリンターの精度が上がっていったときに、写真の方がいいと判断すれば、考えるかもしれないけど、手作業で描く意味として、どうたらこうたらというよりは、今のところベストな見え方は、絵画にしたときのほうが、魅力的にできるという自分の自負みたいなのはあって、それで絵画にしています。
- 石崎:
-
絵画の話が続いたので、次は中野さんに。
- 中野:
-
鈴木さん、よろしいでしょうか? さっきおっしゃっていた、具象彫刻であるということをコンセプトにしっかり落とし込んで制作しているということはすごいと思いました。その前に、人物像を、なぜか作っちゃうという風におっしゃっていたんですけど、それはなんでなのかな?と。 僕もそういうところがあって、なぜか人物を追いかけていっちゃうんですけれど…。
- 鈴木:
-
人物を作ったのは、話は戻っちゃうけど、造形大学に入ってからで。基本的に小さいときにおもちゃとか、ガンダムのプラモデルとかウルトラマンのフィギュアで育ったので、人型に対する愛着はあるんだろうなと思います。それで、考えてみると、先におもちゃがあって、そのあと造形大学でロダンを学んだという感じなので…。僕、「作ってしまう」って言いましたっけ?
- 石崎:
-
どうしても人間が出てきちゃうって言ってましたよ。
- 鈴木:
-
…(笑)。
- 中野:
-
いいんです。気持ちはわかります(笑)。あと、例えば発表するかどうかというところは別にして、あのサイズのものより大きいものを作るとか、そういうことが、ドローイングとかエスキースの中で出てくることはありますか?
- 鈴木:
-
あまりないですね。
- 中野:
-
それはやはりプラモデルとか、フィギュアみたいなところで育ってきているので、そのサイズのものでと。
- 鈴木:
-
自分の中でコンパクトスカルプチャーという概念があって、いかに小さい彫刻でパワーが持てるか、空間を支配できるかということにおもしろさを感じているんです。大きくすると値段は高くなるけど、だからなんなんだという部分がいつもあって、なるべく小さくても空間を支配できるようなものが作りたいというのがまず先にあって、そこに具象彫刻があってということなんです。どちらかというと、先に頭の中で考えているというか、なにか形になって出てくるまでは、ドローイングもしていないし、どうやったら空間を支配できるかなというのが先にありますね。
- 中野:
-
ありがとうございます。
- 石崎:
-
鈴木さんは先ほど3Dプリンターが驚異だとおっしゃっていたじゃないですか。鈴木さんの作品は、実在の人を3分の1ぐらいの大きさにする、リアルにするということで、かなり3Dプリンターが得意な分野じゃないかなと思うんですけれども。そういう差別化とかどういう風に考えていますか?というのも、コンパクトスカルチャーは3Dプリンターが一番得意なところなので、ちょっと厳しいですよね?
- 鈴木:
-
そうですね、厳しいですね(笑)。でも、じゃあ、3Dプリンターで作ったものと自分が作った作品を並べたときに、本当に同じものができあがるのかといったらできないと思うんですよ。なぜかというと、使っている道具も違うし、3Dプリンターは色と形でしか判断していないですよね。人間は五感で判断しているはずだから、捉え方が違うと思うし。あとは、道具になってしまうんだけど、やっぱりノミ跡とか、3Dプリンターでは出せないんじゃないかな、最終的に。3Dプリンターで同じものを作ろうとしてもかまわないけど、本質的に同じとは思わないですけどね。
- 石崎:
-
どうもありがとうございました。では、箱嶋さん、どなたかに質問はありますか?
- 箱嶋:
-
続いて鈴木さんに質問をしたいのですが、作家紹介のところに、モデルと20回以上ものセッションを重ねながらとあるのですが、まず、モデルをどう選んでいるのかというところと、モデルとどのようにセッションをしているのかということが知りたいです。
鈴木:友だちに紹介してもらったりとか、街を歩きながら探して、ポートフォリオを見せたりして、スタジオに来てもらいます。やり方としては古典的な方法というか、しっかりモデルを観察して、彫刻を作るということで、その中で、いろいろな世間話とか、過去の体験談とか話を聞いていると、それが彫刻を作りながら吸い込まれていくというか、彫刻に何か含まれていくんじゃないかと思うんですけど。
- 石崎:
-
モデルがいるという点では箱嶋さんも同じだと思うんですけど、箱嶋さんはモデルさんとそうしたやりとりはない…、一瞬の出会いが全てですよね。
- 箱嶋:
-
私もやり取りがあるとおもしろいなと思ってはいて、どういう風なのかなと思いました。
- 石崎:
-
そろそろ時間が近づいてきたんですけど、会場から作家さんにご質問とかがあれば。せっかくのまたとない機会ですので、学生さんも、先輩に聞きたいことがあれば…。
- 会場1:
-
コレクターの○○と申します。薄久保さんにお聞きしたいんですけれど、東京に住んでおられて、京都にうつられて、さっき河井 寛次郎さんというお話も出ていたんですけれど、京都ってすごく歴史がありますよね。そういった中で、アートを作る上での京都が持っているオーラは感じますか? 自分の作品になにか影響を受けるようなもの、さっきスピリチュアルとは違うと言っていましたけど、そういった気とかオーラみたいなのはどうですか?
- 薄久保:
-
私は京都といっても、市内から少し離れた田舎に住んでいるのですが、市内にも毎週行きます。京都は、世界の人気都市ランキングにも最近なったじゃないですか。ありとあらゆる人を呼び寄せてしまう「気」みたいなものというのは、あるのかなと思います。そういう部分は自覚的になる部分ではないんですけど、潜在的に京都に引っ越した影響は大きくて、街を歩くとすぐに国宝や重要な美術芸術関連の作品も見られますし、神社仏閣もありますし、そういうところに足を運ぶことで、すごく大きい影響があるような…。まだ予感ぐらいなんですけどね、まだ一年ちょっとぐらいなんで。ある感じがします。目に見える視覚的な美術だけじゃなくて、思想の部分でかなり惹かれる部分があって。私も海外などで作品を発表するうえで、言葉の重要性をかなりひしひしと考えています。西洋ベースのコンテキストにのっとりながらの解説をするうえで、日本人が近代以降だけではなく、もともともっている思想的な部分、人間中心的ではなく、言葉数が少ないようなところを、きっちりと翻訳して伝えることができれば、十分、それは日本のオリジナリティとして伝えることができると思います。日本の作家はそれをすごくやっているし、出来ていると思います。ただ、言葉ではない感覚的問題という風に片付けてしまうと、やはりロジックの強い西洋側から見ると、それはそれで下の方に見られてしまう部分があると思うのです。そこをきちんと整理して言葉にして、ていねいに伝えることができればいいなと思っています。
- 石崎:
-
翻訳の仕方も薄久保さん自身模索しているという感じですか?
- 薄久保:
-
そうですね。結構考えていますね。
- 石崎:
-
もう一方ぐらい、質問を受けられますが、いますか? 特に学生さんとか?
- 会場2:
-
今回、「絵画と彫刻のあり方」という相対的なテーマがついているので、今学んできた彫刻のテクニックとかという話もありましたけど、いわゆる絵画と彫刻というものが、同一のものではなくて、差異があるものとして認識しているのか、また、同じ方向に向かっていくのか、その在り方をうかがいたいなと。僕自身は個人的には、違うものだという認識でいるのですが。
- 大畑:
-
今回テキストを僕が実は書いていまして、結論からいうと、絵画と彫刻の違いという感覚が僕には全くない。アートというくくりでくくっちゃってもいいぐらいだと僕は思うんですけど。逆にそうしていかないと、今の美術の流れもつながっていかない気がしていて、つながれば、改めて過去の彫刻や絵画のことも理解できると考えています。特にこの造形大学での試みなんですけど、さっき鈴木さんも言ってましたが、すごく特殊なことを未だにやっているというところが、特に彫刻ではありえると思っていて。逆にそれを売りにするためには、きちんとその時代に戻ることも必要ですし、同時に、今の時代の感覚というものをもちながら関わっていくということが、あえてアカデミックなことを経験するからこそ、軸ができるんじゃないかなと思って、今回そういうタイトルにしました。
- 石崎:
-
企画者ご本人にいい形でまとめをしていただきましたので、今回はここで終わりにしたいと思います。この展覧会では、今質問にもあったように、「絵画と彫刻のあり方」という非常に大きなテーマの展覧会だったんですけど、その中で具体的なレベルで非常に真摯な絵画なり彫刻なりへの、出品作家の方々の問いかけの見られる作品が1階の展示会場に並んでいると思います。引き続き、18時からこの展覧会のレセプションとして会がありますので、そこでまたみなさん、質問を作家さん本人に投げかけていただくことも可能ですので、みなさん作品を目にした感想などをもとに交流していただければと思います。みなさん、ご静聴ありがとうございました。